第38回 食支援とそのプロフェッショナル
公開日:2025/05/19
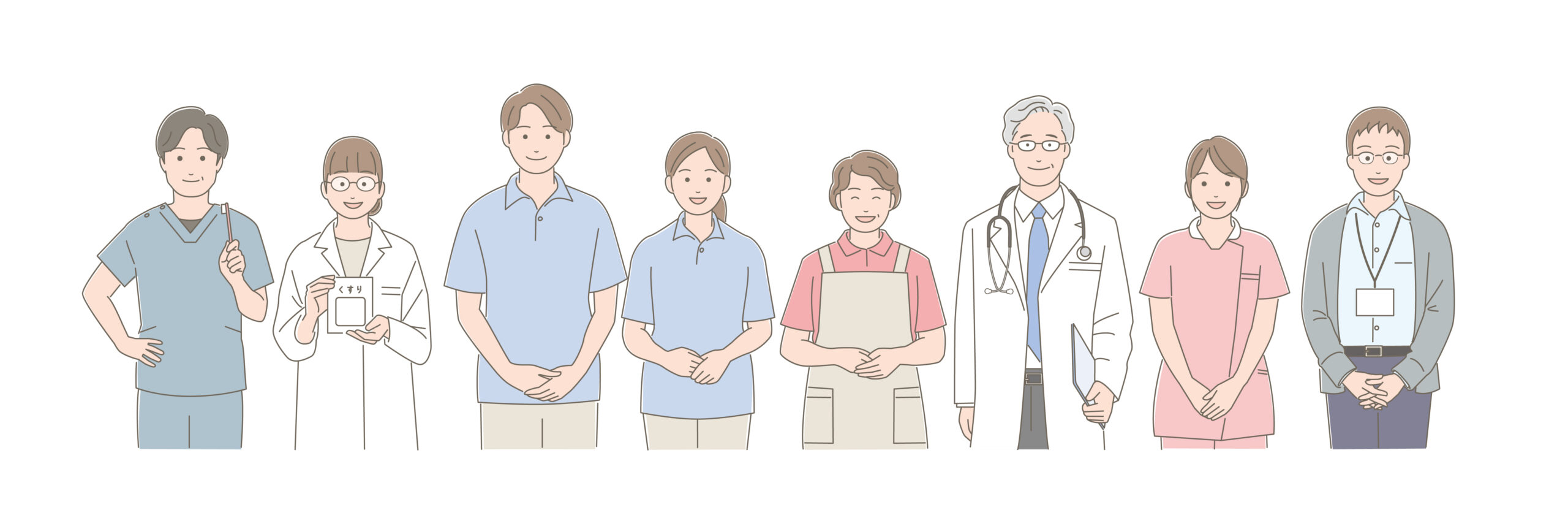
食支援の定義
介護の経験がある方でしたら理解できると思いますが、高齢や様々な病気などが原因で口から食べられなくなることがあります。前回も少しお話しましたが、食べられなくなる原因を少し挙げてみます。
- 食べる機能が低下
- 全身の筋力(体力)が低下
- 口の環境が悪い
- 食事姿勢が悪い
- 栄養状態が悪い
- 薬の副作用
- 認知機能の低下
- 食事介助が悪い
イメージがわくでしょうか。このようにいろいろな要因で口から食べられなくなることがあります。このような状況であっても口から食べられるようにする支援があります。それが食支援です。ただ、単に食支援というととても幅広くなってしまいます。例えば、食糧不足の地域へ食料を送るといったことも含まれてしまいます。
ここでは、高齢や病気などで機能的に口から食べることが難しくなった方への医療、介護的な支援と限定していきたいと思います。そこで、今後私がこの連載で使用する食支援の定義を次のようにします。
「本人・家族の口から食べたいという希望がある、もしくは身体的に栄養ケアの必要がある人に対して適切な栄養摂取、経口摂取の維持、食を楽しむことを目的としてリスクマネジメントの視点を持ち、適切な支援を行っていくこと」1)
この定義は、私たちが東京都新宿区で多職種の食支援活動を開始する時に作成した定義です。
「本人・家族の口から食べたいという希望がある、もしくは身体的に栄養ケアの必要がある人に対して」というのは食支援を受ける対象者です。口から食べたいという希望がある、ということは現在十分に食べられていない人です。そして支援ですから本人やご家族の希望があるから介入できます。
もう一つ着目しているのは栄養ケアの必要がある人。実は栄養状態が悪くなり、それが引き金になって口から食べられなくなる人もいます。現在は口から食べられていても、栄養状態が悪い方へ早めに介入していくことも重要です。
「適切な栄養摂取、経口摂取の維持、食を楽しむこと」が目的です。栄養管理は食支援の大きな目的になります。また、とても重要視しているのは食を楽しむことです。食べる機能が低下すると柔らかい食事や飲み込みやすい形態の食事になってしまうことがあります。その見た目が食欲をそそらず、食事したくないという方は多くいます。本当に食を楽しんでいただくために食事を工夫したり、より普通食に近い形の食事をとっていただくための支援をしたりするのも重要な食支援です。
具体的な食支援とプロフェッショナル
具体的な食支援とそれを担う職種を挙げてみましょう。
●全身管理
そもそも体調が悪ければ口から食べることができないので、しっかりとした体調管理をしていく。医師、看護師、薬剤師など。
●栄養管理
前述したように栄養管理は重要。管理栄養士など。
●口腔環境調整
歯がなかったり痛みがあったりすると食べられない。むし歯の治療や入れ歯の作製などしていく。歯科医師など。
●口腔ケア
口の中を清潔にしておくことは重要。歯科衛生士など。
●摂食嚥下機能のリハビリ
いわゆる食べる機能の訓練。言語聴覚士など。
●食事姿勢の調整
食事するときの姿勢が悪く、全身が緊張し食べられなくなることがあります。理学療法士、作業療法士など。
●食事環境調整
机や椅子、箸など食事の周囲環境を整えます。福祉用具専門相談員など。
●食事形態の調整
普通食が食べられないとき、その方の機能に合わせた食事形態に調整します。言語聴覚士、管理栄養士など。
●食事作り
実際の食事を提供します。ご家族、介護職、調理師、配食弁当サービスなど。
●食事介助
自分で食事ができなくなった方への介助。介護職など。
このように、様々な支援とそれを担うプロフェッショナルがいます。次回以降、具体的な食支援についてわかりやすく解説していきます。
1)五島朋幸:最期まで食べられる街づくり.静脈経腸栄養.Vol.30,No.5,P1107-1112,2015.
五島朋幸(歯科医師/食支援研究家)
1965年広島県生まれ。
ふれあい歯科ごとう代表、新宿食支援研究会代表、日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科臨床准教授。株式会社WinWin代表取締役。
1997年より訪問歯科診療に取り組み、2003年以ふれあい歯科ごとうを開設。
「最期まで口で噛んで食べる」を目指し、クリニックを拠点に講演会や執筆、ラジオのパーソナリティも務める。
Contents
- Introduction
- 第1回「ボーっと食べてんじゃねーよ!」
- 第2回「噛めば噛むほど」
- 第3回「噛むことと認知症予防」
- 第4回「美味しさの正体」
- 第5回「飲み込みと姿勢」
- 第6回「飲み込みの動き」
- 第7回「飲み込みが悪くなったときにできること」
- 第8回「口から食べるための訓練」
- 第9回「食事の工夫」
- 第10回「舌の役割」
- 第11回「入れ歯の話①」
- 第12回「唾液の話」
- 第13回「口腔ケアのその前に」
- 第14回「口腔ケアの意義と効果」
- 第15回「誤嚥性肺炎予防」
- 第16回「口腔ケアの効果②」
- 第17回「口腔ケアグッズ」
- 第18回「口腔ケアの実際」
- 第19回「口腔ケアが困難な事例」
- 第20回「入れ歯の口腔ケア」
- 第21回「認知症と口腔ケア」
- 第22回「認知症と口腔ケア(実践編)」
- 第23回「認知症と入れ歯」
- 第24回「食べることと薬」
- 第25回「入れ歯の話②」
- 第26回「入れ歯と誤嚥性肺炎」
- 第27回「口腔内の変化」
- 第28回「残根の話」
- 第29回「口腔ケアグッズ②」
- 第30回「口腔ケアグッズ③」
- 第31回「ブラッシング法」
- 第32回「機能的口腔ケア(唾液腺マッサージ・嚥下体操など)」
- 第33回「食事介助」
- 第34回「SSK-O(食べる機能と食事の形態)判定表」
- 第35回「食事動作」
- 第36回「食支援とは」
- 第37回「食べることとリスクマネジメントの話」
- 第38回「食支援とそのプロフェッショナル」
- 第39回「多職種の食支援」
- 第40回「サルコペニア」
- 第41回「食事と環境と姿勢」
- 第42回「食べる機能の評価」
- 第43回「噛むことの評価」
- 第44回「飲み込みの評価」
- 第45回「食べることと薬の関係」







