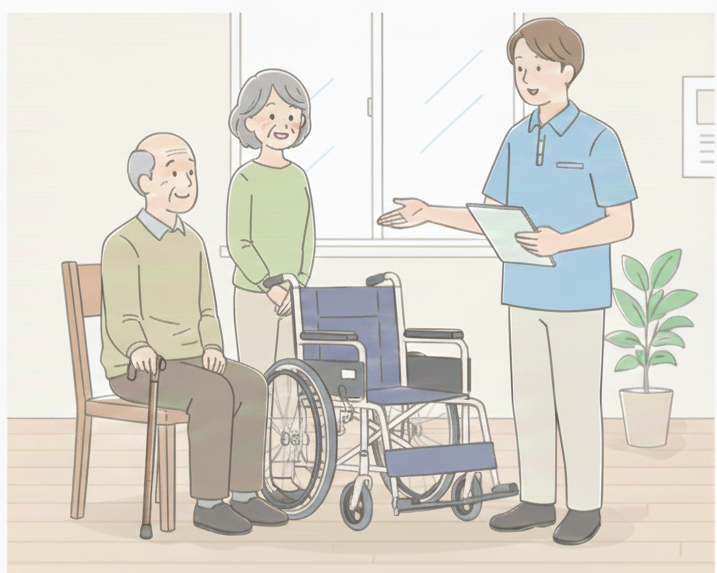高齢者の脱水症状を防ごう!脱水症状を起こす5つの原因と予防法
公開日:2025/05/01

在宅で高齢者を介護する方にとって、脱水症状は気がかりなことのひとつでしょう。
高齢者は脱水症状を起こしやすく、ひどくなると命に関わる場合もあります。しかし、早く気付いて適切な対応をすれば、症状が悪くなるのを防ぐことができる可能性があります。
この記事では、高齢者の脱水症状の特徴、原因、そして家庭でできる予防法を詳しく説明します。この記事を読むことで、高齢者の脱水症状についての知識を深め、日々の介護に役立ててください。
高齢者の脱水症状
高齢者の脱水症状は、若い世代とは異なるいくつかの特徴があります。これらの特徴を理解しておくことで、高齢者の脱水症状を早期に発見し、適切な予防と対策をおこなうことができるでしょう。高齢者特有の脱水症状のサインを見逃さないように、次のポイントを確認してください。
高齢者の脱水症状
高齢者の脱水は次の3つのいずれかが発生することで起こります。
1.水分摂取量が減少している
2.水分を失う量が増加している
3.この両方が同時に発生する
つまり、高齢者は水分を摂る量と水分が身体から出る量のバランスが崩れやすいため、脱水になりやすいのです。
高齢者は口の中の感覚が鈍くなっていると言われているため、のどが渇きにくく、その結果、水分を摂る量が少なくなりがちです。 さらに、おもらしや夜間のトイレを気にして、水分を摂るのを我慢してしまうこともあります。高齢者を日々、観察する中で、いつもより口数が少ない、反応が鈍いなどの脱水症状のサインを見逃さないようにすることが、早期発見につながります。
特に夏季は脱水症状に注意する
夏は気温が高く、汗をかく量が増えるため、脱水症状が起こりやすい季節です。
高齢者は室内にいても脱水症状が出たり、熱中症になったりすることがあります。なぜなら、高齢者は体温を調節する機能が低下しているため、暑さを感じにくくなっている場合や、暑さを我慢してしまう場合があるからです。
実際に「クーラーの風が嫌いだからつけない」「扇風機を回しているから問題ない」と考えている高齢者もいます。ほかにも、住んでいる家屋が古くクーラーをつけていても室温が下がらなかったり、クーラー自体が古く効果がなかったりなどのケースも少なくありません。
通常、人間の身体は体温が上がっても発汗や皮フ血管の拡張で、体温が外へ逃げるようになっており、体温調節が自然とおこなわれます。
しかし、熱中症ではこの体温の上昇と調整機能のバランスが崩れ、身体に熱がどんどん溜まってしまい、めまいや吐き気などの症状があらわれます。なかには、けいれんしたり、意識を失ったりすることもあるため注意が必要です。
そのため、室温や湿度を適切に管理し、高齢者が快適に過ごせる環境を整えましょう。エアコンや除湿器の活用や、直射日光が当たらないようにしたり、こまめな換気も忘れずにおこない室内に熱がこもらないようにする工夫も大切です。
冬季も脱水症状が起こる
冬は空気が乾燥し、暖房器具を使うことで室内がさらに乾燥しやすくなります。乾燥は身体の水分を失うことにつながるため、脱水症状を引き起こす原因になります。
冬季は若い人でも水分を摂る機会が減りやすいですが、高齢者はさらに摂らなくなりがちです。
冬もこまめに水分補給をすることに加え、加湿器を利用したり、濡れたタオルを干したりして、室内の湿度を保つことも大事です。
チェックリストと高齢者が脱水症状を起こしやすい主な5つの原因

高齢者が脱水症状を起こしやすい原因は主に5つあります。それぞれの原因を知り、日々の介護で注意していきましょう。
脱水症状をチェックリストで確認してみよう
チェックリストを用意しました。チェックする項目が多い高齢者ほど、脱水症状を起こしやすいため注意してください。
| 手が冷たい | |
| 口の中や唇が乾燥している | |
| ハンカチを拾うように手の甲をつまんで、つまんだ跡が消えるまで3秒以上かかる | |
| 親指の爪の先を推して赤みが戻るのに3秒以上かかる | |
| ワキが乾燥している | |
| 尿の色が茶色で濃い |
参考:厚生労働省/職場のあんぜんサイト(PDF)
日本医師会/かくれ脱水に注意-自分でできる簡単なチェック法(PDF)
全国訪問看護事業協会/ 防ごう!守ろう!高齢者の脱水(PDF)
ただし、これらはあくまでも脱水症状を疑う際の目安です。症状が疑われる場合は、病院の受診を検討しましょう。
体内の水分量が減っている
年を重ねるにつれて、身体の水分量が減っています。
筋肉は多くの水分を含んでおり、体内の水分量を保っています。しかし、加齢により筋肉量が減少すると、それに伴い体内の水分量も低下していきます。また、体内の水分量を調節する腎臓の機能も加齢とともに低下してしまい、老廃物を排泄するためにたくさんの水分(尿)が必要となります。
つまり、高齢者は身体のなかに水分を保持する力も弱くなるのです。
そのため、高齢者は、わずかな水分不足でも脱水症状を起こしやすくなります。高齢者は脱水症状を起こしやすい状態にあることを理解しておきましょう。
水分摂取量が不足している
高齢者は、食欲がなくなったり、飲み込む力が弱くなり誤嚥を恐れたりするなどの理由で、食事や水分を摂る量が少なくなりやすくなります。
トイレに行く回数を減らしたいと考え、水分摂取を控える高齢者もいます。
さらに、高齢者が認知症の場合は「水は飲まなくても大丈夫」と判断してしまうこともあり、水分を摂らない傾向があるため注意が必要です。
下痢やおう吐などによる水分が失われている
高齢者の場合、下痢やおう吐による脱水は、若い世代に比べて急速に進行するリスクがあります。これは、前述の通り、高齢者の体内水分量が少なく、下痢や嘔吐による脱水症状をカバーする能力が低下しているためです。
特に、寝たきりの高齢者や、自分で水分を摂取することが難しい高齢者の場合は、注意深い観察と早期の対応が求められます。
下痢が続く際には、便の回数や性状だけでなく、皮フの乾燥状態や尿量の変化も確認しましょう。おう吐がある場合は、おう吐物の量や回数、水分摂取の状況などを記録しておくと、医療機関に伝える際に役立ちます。
おう吐した場合に経口補水液を与える際は、一気に大量に飲ませるのではなく、少量ずつ、時間をかけてゆっくりと与えるようにしましょう。吐き気がある場合は、無理に飲ませると再びおう吐を誘発する可能性があるため、医師に相談しながら、適切な方法で水分補給をおこなうことが大切です。
加齢によってのどの渇きに気付きにくい
高齢者は、年を取るにつれてのどの渇きを感じにくくなるため、水分補給が遅れ、脱水症状が進みやすいです。
そのため、高齢者の体調の変化に注意し、脱水症状の早期発見に努めたり、家族や周りの人が高齢者の水分補給を促したりしなければなりません。
また、のどの渇き以外の脱水症状のサインに気付きにくい場合があります。
尿の回数や量の変化、皮フや口の乾燥、便秘などの症状にも目を配ることが大切です。
服用している薬の影響がある
高齢者は、服用している薬の影響で脱水症状を起こしやすい場合があります。
東京都健康長寿医療センターの調査によると、75 歳以上の約8割が2疾患以上、約6割が 3疾患以上の慢性疾患を併存していることが明らかになりました。 高齢者はいくつかの病気を持っている方が多いと言え、薬の量も自ずと増えがちです。
例えば、利尿薬は尿の排出を促し、体内の水分量を減少させます。また、降圧薬は発汗を促す可能性があり脱水につながります。これらの薬の影響で、体内の水分と電解質のバランスが崩れ、脱水症状を起こしやすいのです。
在宅で高齢者の脱水症状のサインを見分ける方法!早期発見のためにやるべきこと

高齢者の脱水症状は、進行するまで気付きにくい場合があります。しかし、早期に発見し適切な対応を取ることで、重症化を防げる可能性があります。
ここでは、在宅介護において高齢者の脱水症状のサインを見分けるためのポイントと、早期発見のために家族や介護者が日常的に注意すべきことを解説します。
軽度
軽度の脱水症状では、めまいや立ちくらみ、食欲不振などが見られます。これらの症状は日常生活でも起こりやすく、脱水症状だと気付きにくいです。
高齢者の場合、軽い症状でも進行が早いことがあるため注意が必要です。特に、持病がある高齢者や普段から活動量が少ない高齢者は、脱水症状が重症化するリスクがあると考えられます。
「いつもと様子が違って元気がないな」「暑さできつそうだな」など、いつもと様子が違うと感じた場合は、ご家族が高齢者に水分補給を促し、安静にしてもらいましょう。
高齢者の体調の変化を見逃さず、早めの水分補給を心がけることが不可欠です。
中等度
中等度の脱水症状では、唇や口の中の乾燥、皮フの乾燥、尿の量が減るなどが見られます。
高齢者の皮フは薄く、乾燥していることが多いため、皮フの乾燥だけで脱水と判断するのは難しい場合があります。
しかし、普段よりも乾燥がひどい、皮フのハリがないといった変化が見られた場合は、脱水症状を疑わなければなりません。
また、尿の量の減少は、体内の水分が不足しているサインとして重要です。排尿回数や尿の色などを普段から記録しておくと、変化に気付きやすくなります。
高齢者は中程度の脱水症状になると、自分で水分補給ができなくなる場合があるため、ご家族や周りの人が、高齢者の水分補給をサポートする必要があります。
また、中程度の脱水症状でも、意識がぼんやりしたり、けいれんを起こしたりする恐れがあるため、早めに医療機関を受診することが大切です。
重度
重度の脱水症状では、意識がなくなる、けいれん、血圧が下がるなどが見られます。
重度の脱水症状は、生命に関わる危険な状態です。意識がない、呼びかけに応じないなどの症状が見られた場合は、一刻も早く救急車を呼ぶ必要があります。
脱水症状によって電解質のバランスが崩れると、神経細胞に異常をきたしてせん妄(*)を起こすこともあります。
せん妄は、高齢者に特によく見られる症状で、興奮したり、混乱したり、幻覚を見たりすることがあります。これらの症状も、重度の脱水症状のサインである可能性があるため、注意が必要です。
(*)せん妄とは:体の調子が悪くなった時などに、注意する力や理解する力、記憶する力などが急に低下して、状態が変動すること
脱水症状を予防するための具体的な方法
高齢者の脱水症状は、日々のちょっとした工夫で予防できることがあります。ここでは、在宅介護の現場で実践できる、具体的な予防方法を解説します。
これらの方法を日常生活に取り入れることで、高齢者が脱水状態になるリスクを減らし、健康的な生活を送れるようにサポートしていきましょう。
1日に必要な水分摂取量を知る
高齢者の場合の水分量は、1日に2,000mlとされています。
3食分で1,000mlの水分を確保できるため、飲み物からの水分摂取は1,000mlを目安にしてください。
ただし、これはあくまで一般的な目安であり、高齢者それぞれの身体の状況や服薬の内容、1日の活動量などによって必要な水分量は異なります。心臓に病気ある場合や慢性腎臓病で透析を受けている場合などは、水分摂取量が制限されることもあります。
そのため、水分の1日量はどのくらいか、どのタイミングで水分を摂ると良いのかなどについてかかりつけ医に指導を受けるようにしましょう。
のどが渇かなくても水分摂取を心がける
高齢者はのどの渇きを感じにくいため、時間を決めて定期的に水分補給を促しましょう。
具体的には、朝起きた時、朝食時、午前10時、昼食時、午後3時、夕食時、お風呂の時、寝る前など、時間を決めて水分補給の時間を設けると良いでしょう。
一度に大量の水分を摂るのではなく、少量ずつこまめに水分補給することが大切です。
また、水分補給を嫌がる場合は、声かけの工夫も重要です。「お茶にしませんか?」「少しだけ水分を摂りましょうか」など、優しく促すように心がけてください。
水分摂取を促す際には、声かけだけでなく、飲みやすいように工夫することも大切です。例えば、ゼリー状の飲料やとろみをつけた飲み物など、高齢者が無理なく口にできるものを用意しましょう。
運動時・入浴時は特に注意して水分を摂取する
運動や入浴は汗をかきやすく、脱水症状を引き起こしやすいです。
運動前、運動中、運動後、入浴前、入浴後、それぞれのタイミングで水分補給をしましょう。
運動をする場合は、運動前にまず水分を補給し、運動中もこまめに水分を摂り、運動後にも水分補給をするようにしましょう。
入浴時は、入浴前にも同じように水分を補給し、入浴後は失った水分を補うために、再度水分を摂ることが大切です。
特に、高齢者は、体温を調節する機能が低下しているため、夏の時期での屋外での運動や長時間の入浴は、脱水症状があらわれるリスクが高まります。
そのため、高齢者は可能な限り涼しい環境で運動をおこない、こまめな水分補給をするようにしましょう。
食事から水分量を確保できるように工夫する
食事の際には、汁物や水分を多く含む食材を取り入れるなど、食事全体で水分を補給できるような工夫をすることも、脱水症状の予防には効果的です。
食事からも水分を摂ることができるため、味噌汁やスープ、果物など水分を多く含む食品を積極的に取り入れてください。
朝食にはヨーグルトや果物、昼食には汁物、夕食には煮物など、毎食に水分を多く含む食品を取り入れるように工夫しましょう。
ただし、味噌汁を摂りすぎると塩分量が増えてしまい、結果として脱水症状を起こしやすいため、摂りすぎには十分注意しましょう。
野菜にも多くの水分が含まれているため、サラダや和え物なども積極的に献立に取り入れると良いでしょう。
高齢者は、食欲不振や飲み込む機能の低下により、食事の量が減りがちです。そのため、食事から摂れる水分量も減ってしまいます。高齢者の脱水症状を予防するためには、食事からも水分を摂取できるよう、工夫することが大切です。
また、高齢者の食事に悩んでいるご家族は、かかりつけ医やお住いの市区町村の役場「栄養相談室」などで相談すると、食事のバランスや栄養素などを教えてもらえるでしょう。
部屋の湿度や温度を調整する
高齢者のいる部屋の温度と湿度管理は、単に快適さを保つだけでなく、脱水症や熱中症といった深刻な健康問題を防ぐうえで非常に重要です。
特に、寝たきりの高齢者や、後遺症やケガなどにより身体が不自由で自力で体温調節が難しい高齢者の場合は、ご家族や周囲の人がこまめに室温や湿度を確認し、適切な状態を維持する必要があります。
夏場の高温多湿な環境は、発汗を促し、気づかないうちに脱水が進行するリスクを高めます。適切な冷房管理とともに、除湿機能も活用し、湿度を下げる工夫も大切です。
一方、冬場の暖房は室内の乾燥を招き、皮フや呼吸器からの水分が失われやすくなります。加湿器の使用はもちろん、こまめな換気もおこない、室内の空気を入れ替えることで、乾燥を防ぎつつ適切な温度を保つことができます。
高齢者によっては、冷房による身体の冷えすぎや、加湿による不快感を訴えることもあります。
そのため、一律的な管理ではなく、高齢者の様子を観察しながら、本人の状況に合わせた調整が求められます。例えば、薄手の羽織物を用意したり、湿度調整には濡れタオルを干したり、加湿器の噴霧量を調整したりするなどの配慮が必要となる場合もあるでしょう。
実際にクーラーをつけていても窓を開けっ放しにしていたり、クーラーをつけたつもりが実際は暖房が入っていたり、夏の季節にももひきを履いていたりするケースもあるようです。
定期的に温湿度計を確認し、記録を残すことも有効です。これにより、時間帯や天候による変化を把握し、適切な対策を講じやすくなります。
高齢者が安全で快適な生活を送るためには、環境への配慮が不可欠であることを常に意識しましょう。
アルコールやカフェインの摂取に注意する
アルコールやカフェインの摂取に注意することも、脱水症状の予防につながります。
というのも、アルコールやカフェインには尿の量を増やし、脱水症状を引き起こす利尿作用があります。カフェインの多いコーヒーや紅茶、緑茶、エナジードリンクなどの摂取も控えめにするようにしましょう。
高齢者は腎臓の機能が低下している場合が多いため、アルコールやカフェインの影響を受けやすいと考えられます。
水分補給をする際には、水や経口補水液などを選び、アルコールやカフェインを含む飲料を水分補給の替わりとすることは避けるようにしてください。
かかりつけ医に相談し薬を調整する
かかりつけ医に相談して、薬を調整することも脱水症状の予防に有効です。
高齢者は、いくつかの薬を飲んでいる場合が多く、薬の副作用によって脱水症状を起こしやすくなることもあるからです。
特に、尿の量を増やす薬を飲んでいる場合は、かかりつけ医に相談することで薬の量を調整してもらうこともできるかもしれません。
高齢者が服用している薬の中には、利尿作用があるものだけでなく、発汗を促すものなど、脱水症状のリスクを高める可能性のある薬があります。
そのため、定期的にかかりつけ医や薬剤師に相談し、服用している薬の影響について確認することが重要です。
医師の指示なしに、高齢者やご家族の判断で薬の服用を中止したり、1回に飲む量を変更したりすることは絶対に避けてください。
日頃から健康観察をしっかりおこなう
日頃から高齢者の健康状態を観察し、脱水症状のサインを見逃さないようにしましょう。
例えば、バイタルサイン(血圧・脈拍・体温など)や体重、尿の量などを記録しておくと、高齢者やご家族も「いつもとなんか様子が違う」「今日は調子が良くないのかな?」など変化に気づきやすいです。
毎朝、同じ時間に体重を測ったり、定期的に血圧を測定したりすることで、身体の変化を把握しやすくなります。
また、尿の回数や量、色、においなども、脱水症状の早期発見につながる重要な情報です。
これらの情報を記録しておき、何か気になる変化があれば、早めにかかりつけ医に相談するようにしましょう。
脱水症状が疑われたときの対応策

高齢者に脱水症状の兆候が見られた場合、迅速かつ適切な対応が重要です。ここでは、家庭でできる応急処置と、医療機関への受診を検討するべきケースについて解説します。
早期に対応することで、症状の悪化を防ぎ、重篤な状態を回避できる可能性があります。慌てずに、落ち着いて対処しましょう。
経口補水液を摂取する
脱水症状が疑われる高齢者には、速やかに経口補水液を飲ませましょう。
なぜなら、経口補水液は失われた水分と電解質を、効率良く吸収させ、バランス良く補給できるからです。
軽度の脱水状態で、口が渇いている、めまいがするといった症状が見られた場合、経口補水液を少量ずつ、時間をかけて飲むことで、症状の改善が期待できます。
ここで気をつけたいのは、水やスポーツドリンクの補給だけでは脱水症状が改善されないということです。この症状を落ち着くようにするためには、水分の摂取に加えて、ナトリウムやカリウム、カルシウムといった電解質が欠かせません。
しかし、水やスポーツドリンクを飲んでも、電解質を補充できないため対策として不十分です。
また、スポーツドリンクを飲みすぎることで糖分の摂取量が増えるため、脱水症状があらわれたり予防したりするときには、経口補水液を選ぶと良いでしょう。
家庭で脱水症状の初期対応として、特に夏の時期には経口補水液を常備しておくと安心です。ただし、症状が改善しない場合や悪化する場合は、医療機関の受診を検討してください。
涼しい環境になるように調整する
高齢者に脱水症状の兆候が見られたら、まず過ごしている環境を涼しく快適することが大切です。
高齢者は体温調節機能が低下しているため、暑い場所にいると体温が上昇しやすく、脱水症状を悪化させる可能性があります。
具体的には、エアコンや扇風機を利用して室温を下げて、高齢者が過ごしやすいように調整しましょう。
直射日光が当たる場合はカーテンを閉め、風通しを良くすることも大切です。
このように、環境を整えることは、高齢者の身体への負担を減らし、脱水症状の進行を遅らせるために不可欠です。
身体を冷やす
脱水症状が疑われる高齢者には、身体を適切に冷やすことが重要です。
その理由は、熱中症により脱水症状を起こしている恐れがあるからです。炎天下で作業していたり、夏の時期にエアコンの使用を控えたりなど、身体が熱くなっており熱中症が疑われる場合は、体温を下げることで、体内の水分が過剰に失われるのを防ぎ、症状の緩和につながります。。
具体的には、冷やしたタオルや保冷剤を首筋や脇の下、太ももの付け根など、太い血管が通っている部分に優しく当てると、身体を冷やすことができるでしょう。
皮フが弱い高齢者の場合は冷たいタオルや保冷剤を直接皮フに当てると凍傷を起こすリスクがあるため、タオルで包んでから冷やすなどの配慮も必要です。
専門医に相談する
高齢者に脱水症状の兆候が見られた場合は、重症化するリスクが高いため、自己判断せずに専門医に相談することが重要です。
例えば、呼びかけに対していつもよりも反応が悪くボーっとしていたり、尿の量が極端に少なかったり、経口補水液を飲んでも症状が改善しなかったりする場合は、速やかに医療機関を受診してください。医師の診断により適切な治療を受けることが、高齢者の命を守ることにつながります。
また、医師の診察を受けることで、脱水症状を起こした原因を特定でき、今後の予防策を検討する際に役立ちます。
今後も、在宅での介護を続ける場合は、医師や看護師、ケアマネジャーなどの専門家と連携を取りながら、在宅での適切な水分管理や生活指導を受けることが大切です。
ケアマネジャーに相談して新たな介護サービスの導入や住宅の改修などを検討することで、脱水症状を予防につながるでしょう。
まとめ

高齢者の脱水症状は、初期には気付きにくいものの、進行すると重篤な状態を招く可能性があります。
しかし、日頃から水分補給を意識し、体調の変化に注意深く目を配ることで、早期発見と適切な対応が可能です。
脱水症状が疑われる場合は、家庭での応急処置と並行して、速やかに医療機関に相談することが大切です。
正しい知識と対策を持つことで、高齢者が安全で快適な在宅生活を送れるよう、しっかりとサポートしていきましょう。
<参考サイト・文献>
全国訪問看護事業協会/防ごう!守ろう!高齢者の脱水(PDF)
厚生労働省/あんぜんプロジェクト
日本医師会/かくれ脱水に注意-自分でできる簡単なチェック法(PDF)
東京都健康長寿医療センター/75 歳以上の約 8 割が 2 疾患以上、約 6 割が 3 疾患以上の慢性疾患を併存 (PDF)
大学卒業後、集中治療室や心臓血管病棟などで看護師として14年間勤務。主に、急性期の看護ケアに携わる。現在は、3人の子育てをしながら、医療や介護、看護に関わる記事の執筆や監修を行っている。
Contents
【看護師による在宅介護コラム】
▶vol.01 要介護認定から始める在宅介護の基礎知識~要介護認定の基準や申請方法・在宅介護について~
▶vol.02 【認知症介護】在宅介護のポイント!限界と感じやすい3つの理由も解説
▶vol.03 移乗介助―移乗介助の方法・ポイント・注意点などについて
▶vol.04 介護のおむつ交換の手順!9つの注意点や負担を軽減する方法を解説
▶vol.05 在宅介護でよくある5つの悩みとは?介護疲れの対処法と事例を紹介
▶vol.06 高齢者が眠れない原因とは?在宅介護でモーニングケアが大切な理由と基本手順
▶vol.07 要介護者に口腔ケアをする6つの目的!口腔ケアに必要な用品と手順も詳しく解説
▶vol.08 在宅で注意すべき高齢者の転倒とは?5つの原因と対策をご紹介
▶vol.09 高齢者の脱水症状を防ごう!脱水症状を起こす5つの原因と予防法
▶vol.11 【2025年版】在宅介護をする上での高齢者の防災対策|災害時に直面する課題と今すぐできる備え
▶vol.12 高齢者にスキンケアが必要な3つの理由!肌の特徴とトラブルを防ぐケア方法
▶vol.13 在宅介護における高齢者のむくみ対策!症状別の原因とケア方法を解説
▶vol.14 在宅でできる高齢者向けのレクリエーション全17選!目的と簡単にできるゲームも紹介
【介護コラム】
▶vol.01 初めての在宅介護 基礎知識~在宅介護を始める前に~
▶vol.02 介護と介助の違いとは?介助の種類や方法、失敗しないポイント
▶vol.03 介護用品の選び方|在宅介護に必要なものと選び方のポイント
▶ⅴol.04 入浴介助の手順と注意点、必要な介護用品、入浴介助の方法などについて
▶vol.05 車椅子の選び方・使い方、車椅子の介助方法などについて
▶vol.06 清拭(せいしき)の手順について|全身清拭・部分清拭の注意点とポイント
▶vol.07 在宅介護で看取りをするために必要なこと、準備や心のケアなどについて
▶vol.09 排泄介助(トイレ介助)の手順と注意点とポイントについて
▽商品をお求めの方はこちらから(Amazonブランドストア)▽