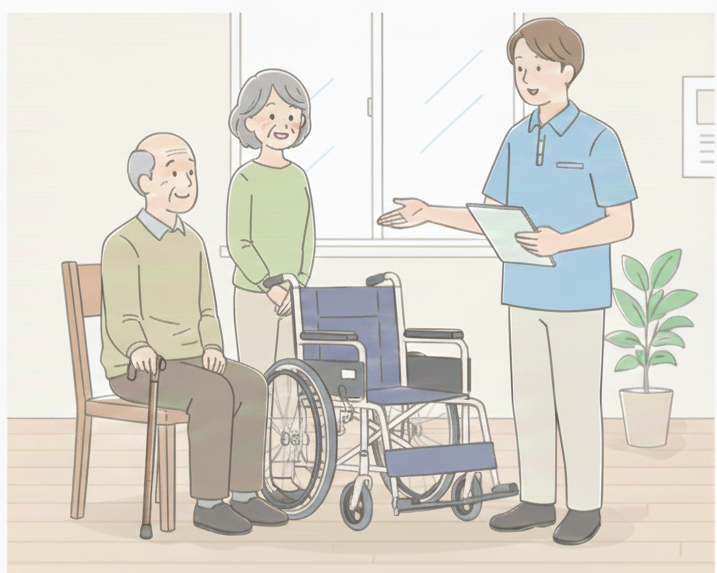第7回「介助を受ければ立てる方」
公開日:2025/07/27

今回は、状態別在宅介護生活のポイント⑤「介助を受ければ立てる方」というテーマでお話していきましょう。
今までお話してきた身体状態に比べて、より介助が必要になってくると本人さま、家族さまの負担も大きくなっていく可能性があります。
このコラムが少しでも在宅介護をする上で参考になれば幸いです。
このレベルからいよいよ本格的な「介護生活」となる
「介助を受ければ立てる」とは、つまり「介助を受けなければ立てない」「ベッドに臥床していればずっとベッド上のまま、車椅子に座っていればずっと車椅子のまま」にならざるを得ない、ということです。立つことに介助が必要ということは、「ベッドと車椅子の間の移り代わり(移乗)にも介助が必要」ということでもあります。必要な時に必要な介助をいつでもできるように、ご家族さまは基本的にご本人さまの近くから離れることができなくなりますし、排泄も介助を受けながら水洗トイレやポータブルトイレを使うことが難しくなります。起立し立位を保つことに介助が必要ですから、下衣の上げ下げを介助する人が別にもう一人必要になってしまいます。したがって、この段階からおむつにならざるを得なくもなってきます。おむつを使わざるを得ない状況が、ご家族さまにもご本人さまにもとても大きな負担になってきます。
このように介護者の負担も一気に大きくなってきますが、この段階でしっかりとした介護が提供されないと「一気に“寝たきり”に」なってしまう可能性が大きくなります。『いや、自分で立てないなら、すでに“寝たきり”ではないか?』と感じられるかもしれませんが、決してそうではありません。「自力では立てないし排泄もおむつ利用だけど、“寝たきり”ではない」そんな状態~生活を目指したいものです。
人力立位移乗介助が困難/負担が大きいならば移乗支援用具の導入を
とにかく移乗介助をしなければベッド上のみの生活となってしまいますから、ベッド~車椅子間の移乗介助の負担をいかに小さくできるか?がとても大切になります。
起立移乗に介助が必要、とはいってもまたその中にいろいろな段階があり、「ご本人さまなりにも頑張ってくれるので少しの介助だけ必要」というレベルから「100%の全介助が必要」という段階までがあり、もちろん必要な介助量が増えれば介護負担も大きくなります。ただ介護負担はあくまでも「ご本人さまの能力と体格」と「ご家族さまの介護能力と体格」との間の相関関係で決まってきますから、ご本人さまの能力がどうであっても一定の介護負担以上であれば『人力だけの移乗介助』を続けることは避けるべきです。
ご家族さまの腰痛や介護事故の原因にもなり結果として「寝かせキリ」になりかねません。福祉用具の『移乗介助支援用具』を早めに導入するべきでしょう。移乗支援用具といえば『トランスファーボード』と『リフト装置』が一般的ですが、在宅介護生活においては『リフト装置』の早期導入をお勧めします。リフト装置とは、本人さまを大きな布シートで包み込むようにしながら半座位の姿勢に上から吊り上げて、ベッド~車椅子間を移動する、というものです。
「え?人を機械で吊り上げるの?」と嫌悪を感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし実態は全く逆で、例えば人力での移乗介助ではお互いに大変で小さな怪我も絶えなかったような状態から、お互いに安楽で本人さまもすっかり安心してリラックスできるようになる、ということが一般的です。もちろん最低限の「使用練習」は必要ですが、在宅介護場面でも少しずつ普及が進んできて、「老々介護」であってもリフト装置を使いながら長期に渡って在宅生活を送っている家庭も増えてきています。
車椅子シーティングや姿勢管理ケアは必須
ベッドから離れる時は当然車椅子を使うことになりますが、このレベルですと「車椅子をご本人さまの状態に合わせ調整する=車椅子シーティング」が必要にもなってきます。最初に使う車椅子を選択し、その上で車椅子背もたれの背張り調整などを行い、安楽に座っていられるように調整する作業です。
これはやや専門的で特殊な技術になりますから、車椅子を準備する段階で車椅子シーティングの技術を持つ「福祉用具の専門家」さんと縁を持つことが大切になります。逆に車椅子が本人さまに合っていないと車椅子に座っていること自体が苦痛なことになってしまい、結果としてせっかく準備したリフト装置も使われることなくベッドに寝かせキリ、となってしまいかねません。
姿勢の面からの食支援も必要になってくることが多い
このように座位姿勢にも問題が生じてくるレベルなのでそのまま食事摂取の問題が生じてくることが多く、そちらにも支援が必要となってきます。基本的な車椅子のフィッティングの他、ただ車椅子に座っているだけの時に比べて食事摂取時には「その方なりに食べやすい姿勢」にしてあげることが必要になる方も多いです。(車椅子座位での食事姿勢変換介助ということ)
また、テーブルの形や高さ、使うスプーンや食器によっても食事摂取状況は大きく変わってきます。項目は多くなりますが、一度セッティングできてしまえば絶えず変えていかなければいけない、ということでもありません。介助方法について、いつでも相談できる相手を持つことが大切です。
また、事情があって「ベッド上での食事摂取を」ということならば、次項の「介護用 ベッドの背上げ機能の使い方」がとても大切になってきます。
介護用ベッドの背上げ機能の使い方について~3モーターベッドの利用を~
医療介護用ベッドには「ボタンを押せば背中があがる」機能があり、それが家具ベッドとの違いです。「ベッドが起きるのならば車椅子はいらないのでは?!」と思われるかもしれませんがまずこれは大きな間違いで、ベッド背上げは車椅子の代わりにはならない、と考えましょう。
ベッド上で背上げ姿勢では車椅子のように下腿(膝から先)を垂らし下すことができず、とても苦しい姿勢になってしまいがちです。背上げボタンを押し続ければ角度で75度程度までベッドの背中は起きますが、どこまで起こせるか?起こしても苦しくないか?は利用者さまごとに違います。
また、同じ角度でもベッドの上のどこに臥床しているか?頭側か?足元側になっているか?でも、全然違ってきます。(ベッドの背上げの軸が背中の真ん中あたりにくると、当然苦しい姿勢になります)また、ベッドで背中~身体を起こす際には必ず「足も上げる」ことが基本です。
これは起き上がった上半身がずり落ちないよう支えるためですね。この「背中をあげる」と「足を上げる」を、同じモーターで行うベッドと、背上げと足上げはそれぞれ別のモーターで行うベッドがあります。前者は「2モーターベッド」、後者を「3モーターベッド」と言います。(もう一つのモーターはベッド高の上げ下げに使われています)
要介護高齢者の在宅生活では「3モーターベッドが基本」です。姿勢調整の自由度が高く、適切な使い方をきちんと定めれば快適に使えます。「2モーターベッド」は健常者が怪我をした時に一時的に使うもの、とするべきです。
介護用ベッドの背上げ機能は、「必要以上に頼りすぎないように、でも使うときには適切に」が基本となります。こちらも詳しい福祉用具の専門家の指導を受けるようにしましょう。
ベッド上起居動作だけでも容易な環境を
例え自分で立つことはできなくても、例えばベッドから自力で起き上がることができるかできないか?起き上がることはできなくても自力で寝返りできるかどうか?その違いもまた、とても大きいです。ベッド上で少しでも自力で動けるように考慮しましょう。
ベッドからの起き上がり動作や寝返り動作のことを「起居動作」と呼びますが、起居動作を自力で行うためには当たり前の92cm幅介護用ベッドとベッド柵だけでは行いにくいものです。現在の介護用ベッドは「介護用ではあっても自立支援にはなりきっていない」のですね。ベッド上起居動作を容易にするためには「余裕のあるベッド幅」がとても大切で、女性高齢者でも92cm幅では自力で動くには狭すぎるのです。楽々と腕を横に伸ばせること、横に腕を伸ばした先にしっかりと掴めるもの(手すり)が必要です。
場合によっては「高価で幅の狭い介護用ベッド」ではなく、「幅が広い家具ベッドに床置き手すり」の組み合わせの方がベッド上で自由にごそごそ動ける、という方が沢山います。この場合は当然「ベッド背上げ機能」は使えないわけですから、ベッドの背上げ機能とベッド上で自由にごそごそできる環境と、どちらがより大切か?検討する必要もあるかもしれません。(ごく少数ですが、幅の広い背上げ機能つき介護用ベッドもあります)
「できること」を大切に!
自力で立つことができないという段階になると、「できること」がどんどん減っていきます。特におむつを使わざるを得ないということについて気持ちがついていかずに、一気に認知症が進行してしまう方も珍しくありません。ですから逆に、少しでもできることを大切にしていきたいですね。認知症の問題がなければ「ベッド上でごそごそできる~自力で寝たまま尿器を使う」という方も時にはいらっしゃいます。たとえ立てなくても、少しでもできることを見つけ習慣としていくことで、必要以上の寝たきり化を避け、より健康的に暮らせていけるようにしましょう。
大渕哲也(理学療法士/介護支援専門員)
1962年新潟県生まれ。
急性期医療機関・慢性期医療機関、特別養護老人ホーム・福祉用具レンタル販売業者等で勤務。
現在は民間介護事業所にて、社内研修・現場アドバイスなどを行なっており、その他民間セミナー業者や各種団体、全国各地の現場からの要請に応じて、研修や現場指導なども行なっている。
Contents
- 第1回 「はじめまして」
- 第2回 「在宅療養介護生活で大切にしたいこと」
- 第3回 「まだ自立レベルでお元気な方」
- 第4回 「歩行に支障が出だしている/認知症初期症状の認められる方」
- 第5回 「歩行に支障が出だしている/認知症初期症状の認められる方 その2」
- 第6回 「実用的には歩けず移動は車椅子だが、自力で立って車椅子へ移る、トイレが自分でできる方」
- 第7回 「介助を受ければ立てる方」
- 第8回 「全介助でも立位は取れない方」
- 第9回 「四肢の変形拘縮があり寝たきりレベルの方」
- 第10回「在宅介護で使う福祉用具① 介護用ベッドその1」
- 第11回「在宅介護で使う福祉用具① 介護用ベッドその2」
- 第12回「在宅介護で使う福祉用具②車椅子その1」