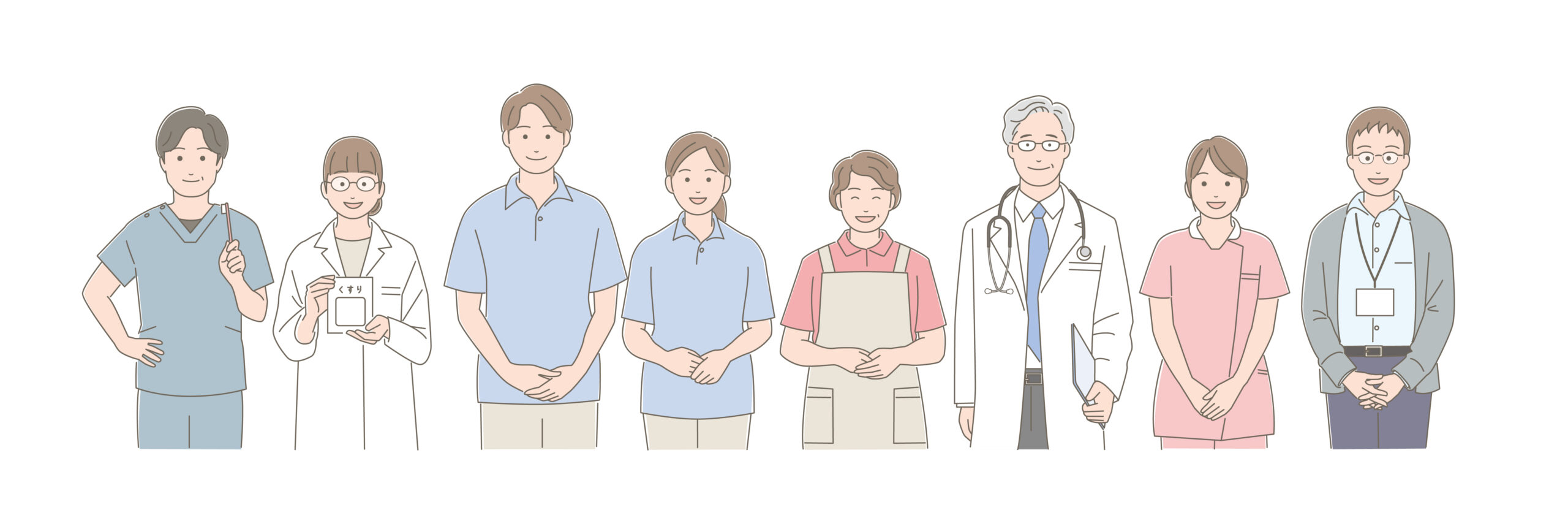第2回 「在宅療養介護生活で大切にしたいこと」
公開日:2025/02/20

「在宅介護は多様」です。一言で「在宅介護」と言っても、その様子は家庭ごとに様々です。要介護高齢者さまの状態、介護者の状態、主な介護者以外の家族の様子、住環境、経済状況などは家庭ごとに異なりますし、都会か田舎か?介護サービスや他の支援制度の整備状況の違いといったその家族の暮らす地域の違いも大きいといえます。
つまり「在宅介護は家庭ごと」なのであって、すべての家庭に共通する「望ましいあり方」のようなものがあるわけではありません。あくまでも「よそはよそ、ウチはウチ」なのですね。まずはそのことを強く意識していただきたいと思います。「介護の本に書いてある通りにするべき」とか「〇〇先生に言われた通りにしないといけない」といった態度で在宅介護に臨むと、すぐに息切れしてしまいます。
それでも、全ての在宅介護家庭に共通する「目標・大切にしたいこと」ということも、確かにあります。例えば時にニュースで報じられる「家庭内介護殺人」や「介護心中」といった悲しい結末は、まずはなにがなんでも避けたい事象です。そういったレベルで、在宅介護にあたるご家族さまの立場から大切にしていただきたいこと、をまとめてみます。
“覚悟”をもつこと
例えばお母さんが赤ちゃんを育てることは当たり前のことと思われます。家庭内でケガ人や病人がでたら、治るまで他の家族がお世話にあたりフォローすることも普通のことです。
では、家庭内に介護が必要な要介護高齢者さまがいる場合、その介護は家族が担うことが当たり前か?となると、そうとは言い切れなくなります。もちろん人それぞれであって、「親の介護はあくまでも子供が担うべきだ」と考える方もいますし、「配偶者の親なんて自分には関係ない」という考えの方もいます。
あくまでも一人一人の価値観の問題であって、同じ家庭内であっても家族ごとに考え方が違うということは、むしろ当然のことです。家族ごとに考え方や価値観が多少違っていても結果として在宅介護をしていこう!となった時には、「これから在宅介護生活が始まることで家庭生活は大きく変わる、色々と苦労や悩みやトラブルも色々と起こる」と覚悟をもつ方が良いと思います。
未経験で苦労や悩みやトラブルの実態も知らないうちから「覚悟」だけはもっていただいた方が、後々のためになります。「こんなはずじゃなかった、こんなことになるとは思わなかった」と先々嘆き続ける方は、最初に「そうなるかもしれない」という想像と何より「覚悟」が足りていなかったのかもしれません。在宅介護生活を始め実態を知って改めて、でも構いません。「自分がやるしかない!」という覚悟は必要だと思います。
加えてもう一言申し添えたいのは、「覚悟」と「諦め」とは違う、ということです。在宅介護生活を担うご家族さまの中で、「覚悟100%、諦めなんてゼロ」という方や「諦めが100%で覚悟はゼロ」なんて方は両方ともいらっしゃらないでしょう。誰の中にも同時に“覚悟”と“諦め”の気持ちは両方あるし、その割合は時によって左右するものかもしれません。でも、「覚悟」はポジティブで前向きなもの、「諦め」はネガティブで後ろ向きなもの、です。いつも前向きでないといけないというのも難しいと思いますが「後ろ向き100%」になってしまうのも、その先は介護殺人や介護心中といった悲しい結末に至る道、ということになりかねません。
ポジティブな態度でいられること
前向きな覚悟をもてている方は、態度もポジティブなものにしていくことができると思います。これは在宅介護にあたるご本人さまはかえって自覚しにくいことかもしれません。しかし、職業者の立場で複数の在宅介護している家庭の支援にあたっていると、この「ご家族さまの態度」も家庭ごとであって様々なご家族さまがいらっしゃることが実感できます。
いつも後ろ向きな諦め気持ちが強くて何事にもネガティブな態度しかとれなくなっているご家族さまもいらっしゃいます。それは「そうならざるを得ない状況」があるからで、そのご家族さまも何らかの支援を受けるべきなのであって責められることではありません。
でも同時に、その方のもともとの性格も影響するでしょう。今さら自分で自分の性格なんて変えられないというのも本当ですが、「ネガティブな態度は結局、損」ということはしっかり認識しておいた方がよいでしょう。自分のくせとして思わず「ネガティブな自分」に陥りそうになった時、「いやいやちょっと待て‥」と少しでも思えることはとても大切なことです。
100点でなくても60点でよし!「継続」を目標に
医療機関内や介護施設内においては「最低限のサービス基準」が定められており、多くの現場では最低限だけではなく、より良いサービスの提供に努めています。しかし、同じことを在宅介護に当てはめてはいけません。
もちろん、在宅介護生活を通じて要介護高齢者ご本人さまの健康が維持され、増進されていけば素晴らしいことです。でも多くの場合その実現のためには、ご家族さまの負担はより大きくなります。「完璧を目指して長続きできず在宅介護生活が破綻してしまう」よりは、ご本人さまもご家族さまも「細く長く安定して生活を送ることができる」ことが何より大切です。
そのためには「100点でなくても60点で良い!」と『前向きに開き直るなおること』です。もちろん、要介護高齢者ご本人さまの生命が危険に晒されるような「介護放置/ネグレクト」状態に陥ることは避けないといけません。しかしだからといって、専門の職業者が「〇〇しないといけません!□□するべきです!」といったアドバイスをしてくれる時、すべて真に受けてその通りにしようとする必要はありません。その時職業者は「100点の方法」を提案しているのですから、介護にあたるご家族さまご自身のこと/要介護高齢者さまのこと/家庭全体の生活状況全体を鑑み、「やり方生活のあり方を変える“余裕”があるか?」をしっかり考えてみることが必要です。
もちろん多くの在宅介護生活支援にあたる専門職は、ご家族さまの余裕も勘案してアドバイスしているはずですが、特に医療職はどうしても要介護高齢者さまのことを中心に考えてしまいがちですし、何より自分自身が在宅介護の経験が無ければご家族さまの苦労を本当の意味では知りません。
アドバイスはアドバイスとして聞きつつも「100点でなくても60点でよし!」を基本とし、時には「それを家族だけで毎日やるのはちょっと難しそうですので、ぜひお手伝いに来てください!」と笑いながら答えられるような余裕を持ちましょう。
最後には逃げてもよい、と思えること
もうすでにお気づきかと思いますがここまでで、「在宅介護生活を始めるにあたっての、あるいは継続していくための心構え」といった内容を書いてきています。
もう少し「心構え」を別の表現/言葉で説明します。それは「いよいよの最後には、“逃げてもよい”と思うこと」です。もちろんそれは、要介護高齢者さまを“見殺し”にすればよい、という意味ではありません。
在宅介護生活において、たとえホームヘルパーさんを利用したりデイサービスやショートステイサービスを利用したとしても、主な介護の担い手はやはりご家族さまです。そこを「施設入所してもらう」、すぐの施設入所が難しければ「できるだけ早く在宅介護を終わらせ別の生活の形に切り替える」ことを大前提にして準備に動く、という切り替えができるかどうか?
「もう無理!」と感じつつ、切り替えの決断ができないままに悲劇的な破綻を迎えてしまう、ということは避けなければなりません。そのためには「いよいよの最後には逃げてもいいんだ」という思いを、心のどこかにもっていましょう。
愚痴ることのできる相手をもつこと
ここまででもうかなりの量を書いていますが、そうはいっても在宅介護生活を送っていく上では時に落ち込んだりネガティブな感情にとわられたりすることもあるでしょう。そんな時に、愚痴ることのできる相手がいるかどうか?はとても大切なことです。
在宅介護生活を送っているのならば、「担当居宅ケアマネ(介護支援専門員)」さんがいると思います。本当は、時には担当ケアマネさんに愚痴ることができるようならばありがたいのですが、それは担当ケアマネさんとの信頼関係やケアマネさん自身の専門職としてのスタンスにもよります。かといって在宅介護の実際を知らない知人友人相手では、愚痴っても「伝わらない」ということもあるでしょう。地域に「在宅介護者の集い」のようなグループがあれば、ぜひ参加してみましょう。
一人で抱え込まないこと、家族で支えあうこと
そして最後には要介護高齢者さま以外の家族間で、支えあえるかどうか?がとても大切です。家庭の中で主に介護にあたる人のことを「主介護者」、その家庭内で最大の決定権を持つ人のことを「キーパーソン」と呼びますが、主介護者は“お嫁さん”(息子の妻)、キーパーソンは“息子さん”ということが多いですね。そうなると結局、「息子さんと妻の間の“夫婦関係”がどうか?」それが在宅介護生活を少しでもストレスを小さく継続していけるかどうか?の最大要因に位置付けてもよいくらいだ、と筆者は考えています。
いかがでしたか?次回からは「状態別在宅介護生活のポイント」シリーズを始めます。
大渕哲也(理学療法士/介護支援専門員)
1962年新潟県生まれ。
急性期医療機関・慢性期医療機関、特別養護老人ホーム・福祉用具レンタル販売業者等で勤務。
現在は民間介護事業所にて、社内研修・現場アドバイスなどを行なっており、その他民間セミナー業者や各種団体、全国各地の現場からの要請に応じて、研修や現場指導なども行なっている。
Contents