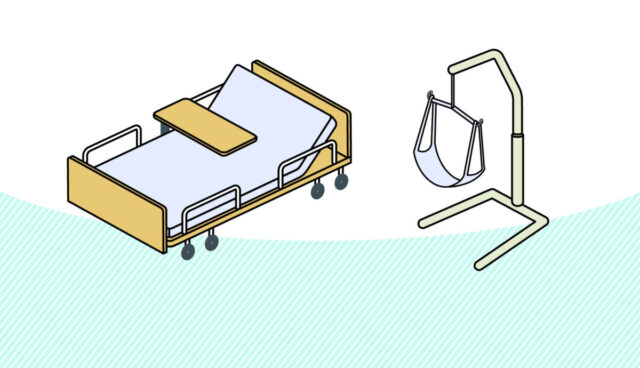第9回「四肢の変形拘縮があり寝たきりレベルの方」
公開日:2025/09/25

今回は、「状態別在宅介護生活のポイント」の最終回となります。例え全く立てない方でも、四肢(腕や足)に変形拘縮が無く意識レベルもはっきりしている方は、前回の「全介助でも立位は取れない方」に該当しますが、腕や足に固まった変形拘縮がある、あるいは意識もはっきりしない状態、あるいは口腔栄養や胃ろうなど経管栄養状態の方は、俗に言う寝たきりレベル、ということになります。
意識のない寝たきりでも、拘縮・褥瘡は予防できる!しかし、上質なケアが必要
例え意識のない寝たきり状態でも、四肢の拘縮や褥瘡を予防~改善することは可能です。そのことは前回に「重度化予防を意識しましょう~臥位ポジショニングケアと体位交換」の節で説明した通りです。しかし現状で病院の病棟や介護施設でも、未だごく一部でしか実践実現できていないことも間違いなく、在宅介護生活で実現するのは難しいかもしれません。でも本当に少数ながらも、ご熱心なご家族さまと支援スタッフグループにより、拘縮・褥瘡の発生を予防できている在宅介護生活家族さまがいらっしゃることも事実です。そんな家庭が増えていくことを願っています。
「尊厳死」「安楽死」を巡る諸問題、まずは「脳死」と「植物状態」の違いについて
今回は「状態別在宅介護生活のポイント」の最終回として、これまでのような技術的なお話よりも、重度要介護高齢者のケアに関する社会的な問題や価値観、政策などについて、まとめておきたいと思います。まず最初に、「脳死」と「植物状態」の違いについて知っておきましょう。
脳死とは?
歴史的に「人の死」とは、「心臓の停止」によって判断されてきました。しかし近年は、「脳死」という概念が広く知られるようになりました。脳死とは、呼吸や血圧の調整、意識など、脳の全ての機能が永続的に失われ、回復の可能性が全くない状態です。人工呼吸器などで一時的に心臓の拍動を維持することは可能ですが、いずれ心臓も停止します。(心臓は、脳からのコントロールが無くなっても心臓の筋肉だけでしばらくは動き続けることができる)
次項の植物状態とは異なり脳幹の機能が失われているため、自力で呼吸することもできず、救命治療法はありません。したがって人工呼吸器で酸素が供給され心臓が動いている状態であっても、実質的には死んでいる状態と同等である、人の死の新しい判定状態である、と言え、本人さまご家族さまの希望によっては「他者への移植のための臓器摘出」が行われることもあります。人工呼吸器を止めればただちに心臓も止まってしまうのですが、ご家族さまにとっては実際にまだ心臓は動いているし体温も保たれている状態のなので、「家族の死」として受け入れがたい、と感じられることもあると思います。
植物状態とは?
それに対して「植物状態」とは、脳の大脳の機能は失われていて意識もない状態ではありますが、脳幹(大脳と脊髄の間の部分)はまだ機能しており、呼吸運動や心臓の拍動、栄養の消化吸収などの生理機能は自力で保たれている状態です。「植物状態」という言葉は医学用語ではなく一般語であって、医学的な傷病名としては「失外套症候群」(外套とは大脳皮質のこと)、症状名としては「遷延性意識障害」(大脳皮質が機能していないので意識は戻らない)と言います。しかし意識がないだけであって、経管処置で水分・栄養を補給さえすれば、生きている状態であることは間違いありません。
長く入院している病院病棟や介護施設に「脳死」の方がいらっしゃることはないです。しかし植物状態の方は、病院病棟や介護施設内で時には10年以上でも生きていらっしゃる方もいます。『寝たきりレベルの方への医療・介護サービスはどうあるべきか?』『尊厳死や安楽死をどう考えるか?』という場合には、まずは「脳死」と「植物状態」の違いをしっかり踏まえることが最低限となります。
近年の一部の論調「医療介護の無駄!」だから安楽死?尊厳死?
ところが近年は脳死や植物状態の違いも踏まえず、極端な言い方をすると「重度な要介護状態になったら医療や介護は無駄!」といった論調が目立ってきています。これには、少子高齢化社会で社会保障費を担ってくれる若壮年者の負担が大きくなってきていること、経済状況に余裕がなくなってきていること、といった社会情勢も大きく影響していますが、同時に個人個人の価値観も影響しています。
「自分で自分のことができなくなったら、あるいは自分で自分のことが分からなくなったら、生きていても仕方ないではないか?!」といった価値観ですね。皆さんはどう考えますか?皆さん自身やご家族さまが「植物状態」になった時、どういう処遇・ケアを希望されますか?
「自分で自分のことができなくなったら、あるいは自分で自分のことが分からなくなったら、生きていても仕方ないではないか?!“だからそうなったら、苦しまないように殺してくれ”」というのが『安楽死』です。しかし、日本では安楽死処置は認められていません。
安楽死が合法化されている主な国には、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、カナダ、コロンビア、スペイン、スイス、ニュージーランドなどがあります。これらの国では、医師による積極的安楽死や、患者が自分で致死薬を服用する自殺幇助が認められています。似ている言葉で『尊厳死』というものもあります。尊厳死とは、回復の見込みのない病状の末期にある患者が、本人の意思に基づき、延命措置を拒否して自然な死を迎え入れることです。これは「人間としての尊厳を保ちながら自然な死を迎える」ことを目的としており、過剰な延命治療を避け、苦痛を和らげる緩和ケアに移行します。
日本では、患者本人の意思を表明する方法としてリビング・ウィル(尊厳死宣言書)があり、本人の意思が尊重される社会の実現を目指して議論が進められています。尊厳死は植物状態になる前の段階でも行い得る、という点が重要です。(緩和ケアによって意識混濁していくことが普通ではありますが)
どちらにしてもあくまでも(元気なころの)「本人の意思」が優先されなければいけません。社会保障費がムダだから安楽死・尊厳死を!という議論は社会的な殺人にほかなりません。
欧米では「寝たきり老人」はいない?!
ところがこの議論の厄介なところは、実は「欧米では、ほとんど寝たきり老人(植物状態・失外套症候群・遷延性意識障害)の方はいない」らしい、ということです。具体的に言うと、「鼻腔栄養や胃ろう、中心静脈栄養で生き続けている方はいない」ということです。もっと具体的に言うと、『介助してあげても口から食べることができなくなった人は、あとは自然に亡くなっていく』のが普通なんだそうです。
これは私には、「消極的な安楽死処置」のように思えますがいかがでしょうか?そして国によってはその延長上に「積極的な安楽死」まで認められているのでしょう。これには、「経済的な問題」や「個人として神様との契約意識を持てているのが人間」といった宗教観が絡んでいると思われます。逆に日本では、山や川、草木にも神さまの存在を感じる八百万の神の国ですね。人の身体も自然の一部であって、意識がなくても「そこに在る」だけで神性を感じる、というのが伝統的な日本人です。(だから、臓器摘出~移植医療が普及しにくいです)しかもここ数十年今でも、日本は世界の中でも経済的に余裕のある国でした。ですから「植物状態の方への処遇・ケアはどうあるべきか?」という議論、あるいはそもそも多数の植物状態の方がいらっしゃる、という国は、世界の中でも日本だけなのです。欧米先進国では「口から食べられなくなったら亡くなる」のですし、日本と似た感性のアジアの国々は未だ日本ほどの経済的な余裕がありません。
個人の「生き方死にざまの検討」と国として「日本流の確立・発信」を
随分大きなテーマのお話となってしまいましたが、要介護高齢者支援という業を真摯に行ってきたからこそ、明らかになってきているテーマでもあります。ここで私たち個人個人と国/業界全体として、今後に備えるべき点を整理してみます。
私たち個人個人と各家庭において
今回説明した通り、医療や介護技術の進化に伴い、「人の死」も様々な形になり得る時代となりました。私たち一人一人が、そして家族の高齢者が「いざ」という時、どういう医療・処置を希望するか?あらかじめ考え、伝えあい話し合っておくことが望ましいでしょう。
例えば具体的には、家族である高齢者が救急搬送された時、どのレベルまでの救命延命処置を望むのか?詳細は本稿では説明できませんが施設入所されている方であれば施設スタッフさんからあらかじめ説明を受けることもできるでしょう。どんなに心を尽くしても、おそらく何らかの後悔は残ります。でも、後悔以上に「やるべきこと/できることはやり切った!」と思えればどんなに幸せなことだろう、と思います。
国/業界全体として考えていきたいこと
長年日本では、ヨーロッパ、特に北欧の福祉が「理想」であるように捉えられてきました。しかし、北欧と日本では社会文化も経済も宗教も全く異なります。北欧から学ぶべきところは学びつつも単にコピーを目指すのではなく、日本社会・文化に根差した医療や介護を考え実践し、形作っていくべきではないでしょうか?「口から食べられなくなったら亡くなるだけ」では、経済効率は良いかもしれませんがあまりに寂しい、と思いませんか?そして今後、経済的にも発展していくであろうアジア諸国に「日本モデル」として自信をもって紹介していける、そんな風に日本の医療・介護が発展していくことを願っています。
大渕哲也(理学療法士/介護支援専門員)
1962年新潟県生まれ。
急性期医療機関・慢性期医療機関、特別養護老人ホーム・福祉用具レンタル販売業者等で勤務。
現在は民間介護事業所にて、社内研修・現場アドバイスなどを行なっており、その他民間セミナー業者や各種団体、全国各地の現場からの要請に応じて、研修や現場指導なども行なっている。
Contents