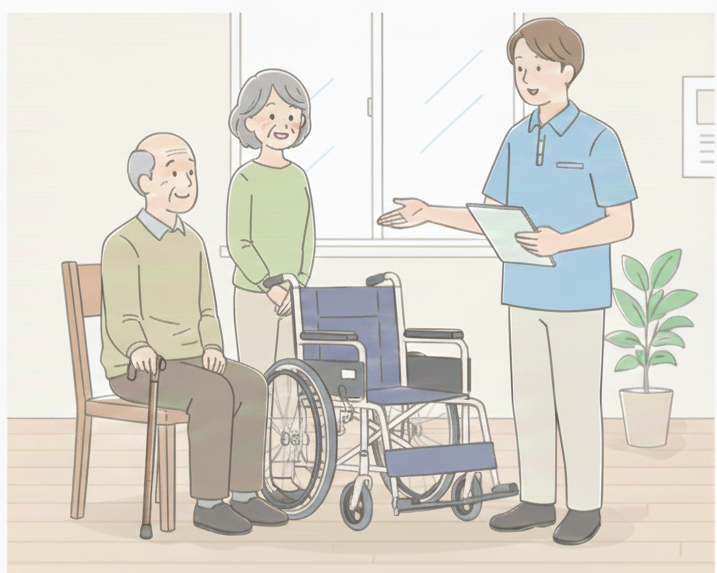【2025年版】在宅介護をする上での高齢者の防災対策|災害時に直面する課題と今すぐできる備え
公開日:2025/07/08

地震や台風、豪雨などいつ起こるかわからないのが自然災害です。要介護の高齢者を支える家族にとって「在宅介護」と「防災対策」は切り離せない大きな課題です。
特に在宅で介護をしている場合、災害時には避難や連絡手段、物資の確保など一般の家庭以上に多くの問題が発生します。そのため、災害に備えて準備しておくことが、命を守るカギとなるのです。
2024年の能登半島地震や各地で頻発する異常気象により、家庭での防災の重要性はさらに高まっています。2025年現在、避難支援制度や介護サービス提供体制の見直しも行われており、改めて、現在の支援情報や地域ごとの避難ルールを知っておくことが、在宅介護世帯での備えとともに重要になっています。
この記事では、在宅介護中の家庭が直面する災害時のリスクと、実践できる防災対策をわかりやすく解説します。この記事を読むことで、在宅介護中の高齢者とご家族が安心して災害に備えられるようになり、いざというときの不安を減らすことができたら幸いです。
在宅介護で高齢者の防災対策が必要な理由
在宅介護をされているご家庭では、災害時に普段よりも大きなリスクがあります。
在宅介護では呼吸器・吸引器・酸素投与など医療的ケアが必要な高齢者もおり、災害時にはこれらの機器が使用できなくなる危険性があります。
2024年1月1日に起きた石川県能登半島地方の地震では、6,520棟もの住宅が全壊しました。全壊していないものの、住宅の一部が壊れたり、停電が発生したりして、在宅介護を続けられなくなったという声がありました。
災害対策基本法に基づく「警戒レベル3」では、高齢者等は避難を開始すべきとされています。 しかし、高齢者は避難に時間がかかるため、避難判断や行動開始が遅れると命にかかわる事態になりかねません。
さらに、災害時には電話やインターネットが使えなくなり、家族や助けてくれる人との連絡が取れなくなることもあります。また、道路が壊れて支援物資が届かなくなることもあります。
このように、在宅介護のご家庭では災害時にさまざまな危険が重なるため、災害が起こる前にしっかりと準備しておくことが欠かせません。とくに、停電したときの電源の確保、必要なものの備蓄、そして家族や支援者と連絡を取る方法などを準備しておけば、もしもの時にも被害を最小限に抑えられるでしょう。
災害が発生した時に介護中の高齢者が直面する問題点

災害時、在宅介護を受ける高齢者は次のような問題に直面する可能性があります。
- 高齢者の身体的な理由で迅速な避難が難しい
- 家族や在宅介護の関係者と連絡が取れない
- 介護・医療用品が足りない
- 避難所での生活に慣れない場合がある
ここでは主な問題点を見ていきましょう。
高齢者の身体的な理由で迅速な避難が難しい
災害時には、高齢者の「迅速な避難」が非常に困難となります。主な理由は、次のとおりです。
- 身体的機能の低下により、歩行が不安定で段差や階段が苦手なケースが多い
- 車椅子や杖、歩行器などの移動補助具を使用しているため、狭い通路や混雑時に避難が遅れやすい
- 車椅子を利用している高齢者は階段や傾斜地の移動が困難で、無理な操作は転倒や事故のリスクを高める
そのため、避難時には支援者の手助けやリヤカーなどの避難補助具が必要です。これがないと避難を諦めてしまうケースも少なくありません。
2021年の避難情報に関するガイドラインの改正により、自治体には要支援者の個別避難計画の作成が努力義務として課され、公共避難支援の強化が進められていますが、現場の対応はまだ十分とはいえません。
そのため、在宅介護中の家庭では、日常的に車椅子移動の訓練をおこなったり、サービスを受けている事業者と避難方法のシミュレーションを実施したりして備えておくことが大切です。これにより、災害時でも落ち着いて、安全な避難行動ができるようになるでしょう。
家族や在宅介護の関係者と連絡が取れない
災害時、高齢者は家族やケアマネジャー、訪問看護師、透析クリニックのスタッフなどの関係者と連絡が取れないという危機的な状況に陥る場合が多くなります。これが在宅介護では特に深刻な課題となりがちです。
たとえば、電話回線が寸断され、ケアマネジャーや行政への連絡手段が数日間断たれ、被災者の多くが孤立状態となった事例もあるようです。適切なケアが受けられなければ、高齢者の病状が悪化し、命にかかわるかもしれません。
さらに、災害が発生したときには、ケアマネジャーや訪問看護師も被災しているケースも少なくありません。スタッフの不足や残されたスタッフの過重労働も連絡がスムーズに取れなくなる要因となり、休日や夜間に緊急連絡ができなくなったり、訪問の回数が1日2回から1週間に3回などと減ったりする可能性があります。
このような状況になると、高齢者はケアを十分に受けられなくなり、その分をご家族が補うケースでは負担は大きくなるでしょう。
介護・医療用品が足りない
災害時、介護や医療が必要な高齢者は、一般的な支援物資だけでは対応できないケースが多い傾向にあります。
在宅介護では、おむつや吸引器、経管栄養剤、インスリンなど専門性の高い用品が必要です。しかし、これらは避難所や災害ボランティアによる配布対象にならず、確保が非常に困難になります。
在宅療養者向けのガイドにも「必要な薬や医療ケア用具、衛生材料、経管栄養剤などの不足」が重要課題として挙げられているのです。
さらに、災害後の物流停止や交通網の寸断により、一般の支援物資では対応できない医療・介護用品の補給が極めて難しくなる現実があります。防災ガイドラインでも、水や食料に加えて、医療・介護用品の備蓄が不可欠と明記されています。
このため、在宅介護をおこなう家庭では、通常使用する薬や用品を最低数日分~1週間分以上の備蓄をしておく工夫が、安全確保の第一歩です。特に、常用薬やおむつ、酸素ボンベ・吸引器のバッテリー、経管栄養剤など専門的な用品を見落とさず、事前の確認が必要です。
避難所での生活に慣れない場合がある
災害時には1週間以上の長期避難が必要になるケースもあり、高齢者にとっては大きな負担となります。多くの避難所がバリアフリー対応未整備で、歩行補助が必要な方の移動が困難になりがちです。
また、不衛生な環境では感染症リスクが高まり、さらに床や段差でのつまずきによる転倒や骨折も多発します。
加えて、標準の避難所では医療機器の使用が難しく、必要な医療処置ができない状況もあるでしょう。
高齢者でも安心できる避難経路・避難場所を事前に確認する
高齢者は避難に時間がかかるため、災害時に慌てず行動できるよう、事前の準備が欠かせません。避難経路や避難所の種類を確認し、自宅から安全に移動できるルートの把握が大事です。
避難所の種類を把握する
避難所には「指定避難所」と「福祉避難所」の2種類があります。それぞれの違いは次のとおりです。
| 項目 | 指定避難所 | 福祉避難所 |
| 主な対象者 | 災害によって自宅で生活できなくなった一般の被災者全般 | 高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦など、特別な配慮が必要な被災者 |
| 設置目的 | 災害発生時に一時的に避難生活を送る場所の提供 | 要配慮者が安全かつ健康的に避難生活を送れるよう、きめ細やかな配慮と支援を提供 |
| 設置場所 | 小中学校の体育館や公民館など、比較的広い公共施設 | 介護施設、病院、福祉施設、ホテル・旅館の一部など、設備が整った場所 |
| 設備 | 簡易的な暖房、毛布、食料、飲料水など、最低限の生活に必要なもの | バリアフリー設備(スロープ、手すり、多目的トイレなど)、介護ベッド、医療機器、専門職員(医師、看護師、介護士)の配置、相談室など |
一般避難所は、災害発生した後、比較的早期に開設されます。その一方で、福祉避難所は一般の指定避難所で生活が困難な要配慮者が受け入れられるよう、準備が整い次第開設されることが多い傾向です。
そのため、在宅でケアを受けている高齢者はケアを受けることが遅れがちです。
また、福祉避難所の申請方法は自治体によって異なりますが、担当窓口で申請書を提出し、医師の意見書や介護証明書の提出が求められるときもあります。在宅介護をしている場合は、早めに自治体に問い合わせ、利用条件や申請手続きの確認が重要です。
ハザードマップを活用する
ハザードマップは、地震・洪水・土砂災害などの被害が予測される区域を示した地図です。
自治体のホームページや防災パンフレットで入手でき、自宅周辺の災害リスクを把握するのに役立ちます。
例えば、自宅が川の近くにある場合は、ハザードマップがどれくらいの深さまで水に浸かるかを確認し、避難経路が安全か、浸水しない別の避難先があるかなどを検討します。裏山や崖の近くに住んでいる場合は、土砂災害警戒区域に指定されていないか確認し、早めの避難が必要な場所かどうかを把握します。
在宅介護中の高齢者は避難に時間がかかるため、事前に浸水や土砂災害の危険性を確認し、安全な避難先の検討が重要です。
万が一のときに迅速な判断ができるよう、定期的に最新情報をチェックし、避難計画の見直しもおこないましょう。
防災マップを活用する
防災マップは、地域の避難所、避難経路、災害時の行動指針を示した資料で、自治体や防災担当部署が作成しています。次のように、具体的なルートを家族で話し合い、実際に通ってみるのも良いでしょう。
- 自宅から一番近い避難所までの道のりに段差や狭い道がないかを確認する
- 車椅子を使っている場合は、スロープがある道やエレベーターが使えるルートを探しておく
- 介護用品を運ぶことを考えて、少し遠回りでも平坦な道を選ぶ
また、最寄りの福祉避難所の場所や受け入れ条件も確認しておくと安心です。家族や介護関係者と情報を共有し、定期的に防災マップを見直してください。
通路を安全にしておく
災害時に高齢者が迅速かつ安全に避難するためには、自宅内の通路をできるだけ障害物のない状態に整備することが重要です。段差や家具、散乱した物品は転倒やつまずきのリスクを高め、車椅子や歩行器を使用している場合は大きな障害となります。
例えば、次のような自宅の工夫をする必要があります。
- リビングから玄関までの通路に敷いている電気コードをまとめたり、家具の配置を見直して通り道を広げたりする
- 玄関の上がりのところに段差解消用のスロープを設置する
- 夜間でも足元が見えやすいよう、廊下や玄関にセンサーライトを設置したり、常夜灯をつけたりする
日頃から通路を整理整頓し、緊急時にスムーズに移動できる環境をつくる努力が、在宅介護の防災対策として欠かせません。
避難行動要支援者名簿に登録しておく
避難行動要支援者名簿は、災害時に支援が必要な高齢者や障害者の情報を行政が把握し、迅速な避難支援をおこなうための重要な仕組みです。
登録によって、自治体からの緊急連絡や避難支援の対象となり、訪問や避難誘導など具体的な支援が受けられます。
登録方法は居住自治体の窓口や地域包括支援センターで申請書を提出し、本人や家族の同意が必要です。医療・介護状況などの詳細な情報の提供で、個別のニーズに沿った支援計画が立てられます。
登録が完了すると、災害時に行政と連携した支援が受けやすくなるため、在宅介護をおこなう家庭には早めの登録がおすすめです 。お住まいの自治体で早めに確認をしておくといざというときも安心できるでしょう。
災害時の連絡手段を共有する
災害時は連絡手段が途絶えやすく、家族や介護関係者との情報共有が困難です。迅速かつ確実に連絡を取るために、普段から連絡方法を決め共有しておく習慣が大切です。
家族との連絡方法
災害時には通信障害が発生しやすく、家族との連絡が途絶えるリスクがあります。そのため、普段から安否確認の手段や、連絡が取れない場合の対応ルールの家族間での共有が非常に重要です。
具体的な対策としては、以下のような準備が有効です。
- 災害用伝言ダイヤル(171)や災害用伝言板(インターネット・携帯電話)の使い方を確認しておく
- 家族全員がその利用方法を理解し、事前に練習しておく
- 通信不能時の集合場所や連絡手段(第三者を通じた連絡など)をあらかじめ決めておく
これらを備えておくと、混乱した状況下でも安否情報を確実に伝え合い、精神的な不安を軽減することができます。在宅介護の家庭では、介護者同士の連携を保つためにも、こうしたルールの周知徹底が不可欠です。
利用中の介護・医療サービスへの連絡方法
災害時に迅速かつ適切な対応をおこなうためには、普段から利用している介護事業者や医療機関の連絡先を正確に把握し、緊急時にもすぐに連絡が取れるよう、管理しておくことが欠かせません。
連絡先は携帯電話だけでなく、冷蔵庫や玄関など家の見やすい場所に大きく目立つ形で貼り出すなどの工夫が必要です。
こうした準備により、災害で混乱している状況下でも、ケアマネジャーや訪問看護、クリニックなどと迅速に連絡が取れ、必要な支援や医療措置を確実に受けられるのです。定期的に連絡先の最新情報を確認し、家族や介護者とも共有しておきましょう。
公的機関への事前相談
在宅介護を安全に続けるためには、災害時に利用できる公的サービスや支援機関への事前相談が欠かせません。地域包括支援センターは、高齢者や介護者の相談窓口として防災対策や避難計画の作成支援をおこなっており、見守りサービスの活用も可能です。
見守りサービスは、災害時の安否確認や支援ニーズの把握に役立ち、早期対応を促進します。
これらのサービスは、自治体によって内容や手続きが異なるため、早めに相談して具体的な利用方法を把握しておくと安心でしょう。
近隣との協力体制の構築
災害時に在宅介護中の高齢者を守るためには、日頃からご近所や民生委員との信頼関係の構築が不可欠です。
顔なじみの関係があれば、安否確認や緊急時の連絡がスムーズになり、迅速な支援が期待できます。
特に、高齢者が孤立しがちな状況では、地域住民同士で助け合う協力体制が生命線となります。民生委員は地域の福祉推進役として、安否確認や情報提供、避難支援の橋渡し役を担う場合が多いため、積極的な連携強化が重要です。
日頃からのコミュニケーションや防災訓練への参加を通じて、災害時にみんなで支え合える体制を整えておきましょう。
在宅介護の環境でできる高齢者の防災準備

在宅介護を安全に続けるためには、日頃からの防災準備が欠かせません。家具の固定や医療機器の点検など、家庭内でできる対策をしっかりおこない、災害時の被害を最小限に抑えましょう。
家具の固定
地震などの災害時に家具が倒れたりものが落下したりすると、高齢者の転倒やけがのリスクが高まります。実際に、次のように固定すると良いでしょう。
- タンスの裏と壁をL字金具で連結する
- 天井と家具の間に突っ張り棒を設置して転倒を防ぐ
- 冷蔵庫や食器棚の扉には開閉防止ロックを取り付ける
- 高い場所にある棚には重いものを置かず落下しても安全なものを選ぶ
固定がしっかりしていないと避難時の障害となるだけでなく、家具の倒壊による重大事故につながるため、専門家の指導のもと確実な設置が重要です。
収納の工夫
災害時の転倒や落下事故を防ぐために「重いものは高い場所に置かない」が基本です。重いものを上に収納すると、地震などで落下し、高齢者のけがや家具の損傷につながる危険があります。ほかにも、次のようなポイントに気をつけましょう。
- 食器棚の上段には軽いプラスチック製の食器やラップなどを収納し陶器や重いガラスのコップは下段にしまう
- 本棚では、厚くて重い専門書などは下の段に置き、文庫本や雑誌は上の段に置く
- キッチンの吊り戸棚には、軽い乾物や使用頻度の低いものを入れ、調味料や鍋などはシンク下の引き出しに収納する
日頃から重いものは下段や床の近くに収納し、軽いものを上に置くなどの工夫を徹底しましょう。安全な避難経路の確保にもつながります。
医療機器の停電への対策
在宅介護では、呼吸器や人工透析機器、ポンプ類など医療機器を使用している場合、停電が生命に直結するリスクとなります。そのため、医療機器の正常な稼働状況を日頃から確認し、停電時のバックアップ体制を必ず準備しておきましょう。
具体的には、非常用電源(ポータブルバッテリーや発電機)を用意し、定期的に作動確認をおこなってください。また、機器の取扱説明書に記載された停電時の対応策を理解し、緊急時に迅速に対応できるよう家族や介護スタッフとも共有することが不可欠です。
さらに、停電時の連絡先や支援体制もあらかじめ自治体や医療機関に確認し、緊急時のサポートが受けられるようにしておくことが安全確保につながります。
こうした事前の備えが、災害時の医療リスクを軽減し、高齢者の生命を守るうえで重要です。
日々のシミュレーション
災害時の混乱を避けるためには、日頃から在宅介護環境での避難シミュレーションが欠かせません。
- 避難経路の確認
- 必要物資の準備
- ご家族と高齢者の役割分担
実際の動きを想定し、問題点の洗い出し・改善をおこなうと、緊急時にも冷静かつ迅速に対応しやすくなります。定期的な訓練が命を守るカギになります。
高齢者に必要な防災グッズ、非常用持ち出し品
災害時における在宅介護の防災対策では、高齢者の命と健康を守るために必要な防災グッズや非常用持ち出し品の準備が不可欠です。迅速に避難するために、必要最低限のものをコンパクトにまとめておく工夫が必要です。
高齢者特有の身体的・医療的ニーズに対応できる内容を次のように準備し、家族や介護者との共有することが求められます。
| 項目 | 説明 |
| レトルトのお粥や水分 | ・調理不要で食べやすいエネルギー源 ・特に温めなくても食べられるものが便利 |
| とろみ剤 | ・飲み込みが困難な高齢者向け ・水分や食べ物、嚥下を助ける補助用品 |
| おむつ | ・災害時の排泄ケアに必要 ・十分な数の用意が重要 |
| 使い捨てトイレ袋 | ・避難所や移動時に衛生的な排泄が可能 ・断水時やトイレが使えない状況でも使用できる簡易トイレ用品 |
| 歯ブラシ 口腔ケアシート | ・口腔内の清潔維持 ・感染予防 |
| マスク | ・感染症対策 ・ほこり対策 |
| 下着類・衣類 | ・1日分程度の着替えを準備 ・衛生状態を保つことが大切 |
| 保険証 マイナンバーカード | ・身分証明や医療機関での手続きに必要 ・介護サービスや福祉支援を受ける際の本人確認にも活用 |
| 常備薬 | ・服用中の薬は災害時に切らさないよう、余裕を持って備蓄 ・処方薬だけでなく、市販薬や予備の服薬補助具も合わせて準備 |
| お薬手帳 | ・医療情報を正確に伝えるために必須 ・医療スタッフとの連携に必要 |
| 医療機器・予備バッテリー | ・呼吸器やポンプなどの機器の停電対策として予備電源を準備 ・長時間の停電に備えて、バッテリーの充電状況や使用時間を定期的に確認 |
| 杖 車椅子などの移動補助具 | ・避難や移動時の安全確保に必須 ・破損しないよう保管に注意 |
| 家族との連絡先 | ・緊急連絡先を書いた紙など、すぐに見られる場所に準備 ・自宅 ・避難袋 ・財布などに分けて保管 |
| 老眼鏡 | ・視力補助具 ・紛失や破損に備えて予備を準備しておくと安心 |
| 補聴器 | ・聴力補助具 ・バッテリーの予備も重要 |
このような持ち出し品は、日頃から一つのバッグにまとめておき、すぐに持ち出せるようにしてください。特に、高齢者の特別な医療ニーズに応じた薬や機器、補助具の準備は、命に関わる重要なポイントです。避難時に慌てて用意しようとすると忘れものが増え、必要なケアが遅れてしまう可能性があります。
また、持ち出し品の定期的な点検・更新も欠かせません。食品の賞味期限や薬の残量、バッテリーの充電状態などを半年に一度程度は確認し、使いやすい状態を維持してください。
家族や介護スタッフとの共有により、緊急時に誰でもすぐに対応できる体制を整えられます。さらに、災害の種類や状況により必要な物資は変わることも念頭におくことが大切です。
防災対策は一度の準備で終わるものではなく、日々の見直しと継続的な意識づけが必要です。特に在宅介護の現場では、高齢者の健康状態や生活環境に合わせた柔軟な備えが求められるため、しっかりと準備を整え、安心して避難生活を送れるよう万全の対策を講じましょう。
在宅避難用の備蓄(ローリングストック)
災害時に避難所ではなく在宅での避難を余儀なくされるケースは少なくありません。特に高齢者が介護を受けている場合、環境の変化にうまく対応できず、慣れた自宅での避難が望ましいとされています。
そこで重要になるのが、長期の在宅避難に備えた「ローリングストック」という備蓄方法です。ローリングストックとは、日常的に使う食品や日用品を多めに買い置きし、使った分だけ新しく買い足して常に一定の備蓄量を保つ方法です。
具体的には、以下のような備蓄品を日頃の買い物の際に余分に購入し、消費しながら補充していきます。
- 常温保存できるレトルト食品や缶詰
- 水や飲料
- 日持ちのする介護食品やとろみ剤
- 衛生用品(ティッシュ、ウェットティッシュ、マスクなど)
- 使い捨ておむつや下着
- 薬やお薬手帳の予備
- 電池や懐中電灯などの防災グッズ
これにより、いざというときに期限切れや腐敗の心配なく、常に新鮮な備蓄品を確保できます。災害時だけでなく、普段の生活でも無理なく続けられるため、高齢者のいる家庭に特に適した備蓄法といえるでしょう。
さらに、在宅介護の特性に合わせて、食事形態や医療ニーズに合った備蓄品の選択が重要です。備蓄品は一か所にまとめておくと管理しやすく、非常時にはすぐに取り出せる状態にしておきましょう。
防災バッグに入れておくのも有効です。また、家族や介護スタッフで備蓄内容を共有し、誰が何を管理するか決めておくと、更新忘れや混乱を防げます。
ただし、ローリングストックには注意点もあります。無理に多く買い過ぎると生活の負担になるため、日々の消費ペースに合わせた量の確保が大切です。また、保管場所の湿度や温度管理にも気を配り、食品の劣化を防ぐ必要があります。
自治体や地域包括支援センターの防災支援情報も活用し、定期的に備蓄品の見直し・補充をしましょう。防災意識を高く持ち、日常生活と防災準備を無理なく両立させることが、在宅介護における高齢者の安全確保に繋がります。
介護用品においても、普段から同じものを使うと肌トラブルがなかったり、家族も扱いやすかったりします。
ピジョンタヒラ株式会社では防災の際にも使える商品がたくさんありますので、是非商品を確認してみてください。
朝用お顔すっきりシートは、朝起きて顔を洗ったように汚れを落とせ、ふき取りながら保湿ケアもできます。コットン100%で低刺激なので、デリケートなお顔にもやさしく使え、水が使えない時も気分をすっきりさせてくれます。
お湯のいらない泡シャンプーは、すすぎ不要で簡単に洗髪ができます。コンディショニング成分配合で髪がきしまず指どおりもなめらかです。水が使えない時でも髪の毛をさっぱり洗えます。
さっと さわやかからだふきは、全身に使える清拭シートです。よれずにしっかり拭けるので、楽にふき取れ、厚手の凹凸シートでやさしい肌ざわりです。天然ラベンダーオイル配合で、保湿もしながら香りで気分もリラックスできるでしょう。
ラクラクおしりキレイミストはトイレットペーパーに吹きかけるだけで、おしりふきにできます。水が止まりウォシュレットが使えない時でも、肌への負担が少なく汚れを落とすことができます。また、よい香りが気分もリラックスさせてくれるでしょう。
まとめ|防災対策は「命と生活」を守るための備え

災害はいつ起こるかわからず、特に在宅介護を受ける高齢者にとっては命の危険だけでなく、日常生活そのものが大きく揺らぐ重大な問題です。
今回ご紹介したように、高齢者が災害時に直面する避難の難しさや連絡手段の喪失、医療や介護用品の不足、慣れない避難所での生活の負担は、一般の人以上に深刻な影響をもたらします。
だからこそ、普段から避難経路の確認や必要物資の備蓄、連絡体制の整備といった具体的な防災対策が欠かせません。
また、家具の固定や医療機器の停電対策、日常のシミュレーションなど、日頃からできる備えも非常に重要です。さらに、家族や地域との連携、公的機関への相談も含めた総合的な対策を講じることで、災害時であっても高齢者の命と生活を守る手助けとなります。
防災対策は一度準備して終わりではなく、定期的な見直し・更新が大切です。高齢者本人だけでなく、介護者や地域社会全体で支え合い、安心できる暮らしを守るための努力を続けましょう。
日々の備えこそが、いざという時の大きな安心と安全を生み出します。
<参考サイト・文献>
内閣府/防災情報のホームページ
大学卒業後、集中治療室や心臓血管病棟などで看護師として14年間勤務。主に、急性期の看護ケアに携わる。現在は、3人の子育てをしながら、医療や介護、看護に関わる記事の執筆や監修を行っている。
Contents
【看護師による在宅介護コラム】
▶vol.01 要介護認定から始める在宅介護の基礎知識~要介護認定の基準や申請方法・在宅介護について~
▶vol.02 【認知症介護】在宅介護のポイント!限界と感じやすい3つの理由も解説
▶vol.03 移乗介助―移乗介助の方法・ポイント・注意点などについて
▶vol.04 介護のおむつ交換の手順!9つの注意点や負担を軽減する方法を解説
▶vol.05 在宅介護でよくある5つの悩みとは?介護疲れの対処法と事例を紹介
▶vol.06 高齢者が眠れない原因とは?在宅介護でモーニングケアが大切な理由と基本手順
▶vol.07 要介護者に口腔ケアをする6つの目的!口腔ケアに必要な用品と手順も詳しく解説
▶vol.08 在宅で注意すべき高齢者の転倒とは?5つの原因と対策をご紹介
▶vol.09 高齢者の脱水症状を防ごう!脱水症状を起こす5つの原因と予防法
▶vol.11 【2025年版】在宅介護をする上での高齢者の防災対策|災害時に直面する課題と今すぐできる備え
▶vol.12 高齢者にスキンケアが必要な3つの理由!肌の特徴とトラブルを防ぐケア方法
▶vol.13 在宅介護における高齢者のむくみ対策!症状別の原因とケア方法を解説
▶vol.14 在宅でできる高齢者向けのレクリエーション全17選!目的と簡単にできるゲームも紹介
【介護コラム】
▶vol.01 初めての在宅介護 基礎知識~在宅介護を始める前に~
▶vol.02 介護と介助の違いとは?介助の種類や方法、失敗しないポイント
▶vol.03 介護用品の選び方|在宅介護に必要なものと選び方のポイント
▶ⅴol.04 入浴介助の手順と注意点、必要な介護用品、入浴介助の方法などについて
▶vol.05 車椅子の選び方・使い方、車椅子の介助方法などについて
▶vol.06 清拭(せいしき)の手順について|全身清拭・部分清拭の注意点とポイント
▶vol.07 在宅介護で看取りをするために必要なこと、準備や心のケアなどについて
▶vol.09 排泄介助(トイレ介助)の手順と注意点とポイントについて
▽商品をお求めの方はこちらから(Amazonブランドストア)▽