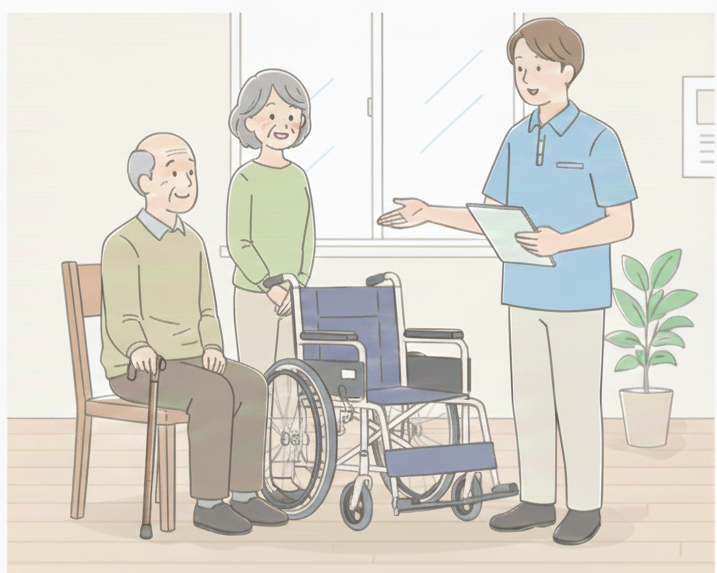第10回 「在宅介護で使う福祉用具① 介護用ベッドその1」
公開日:2025/10/28
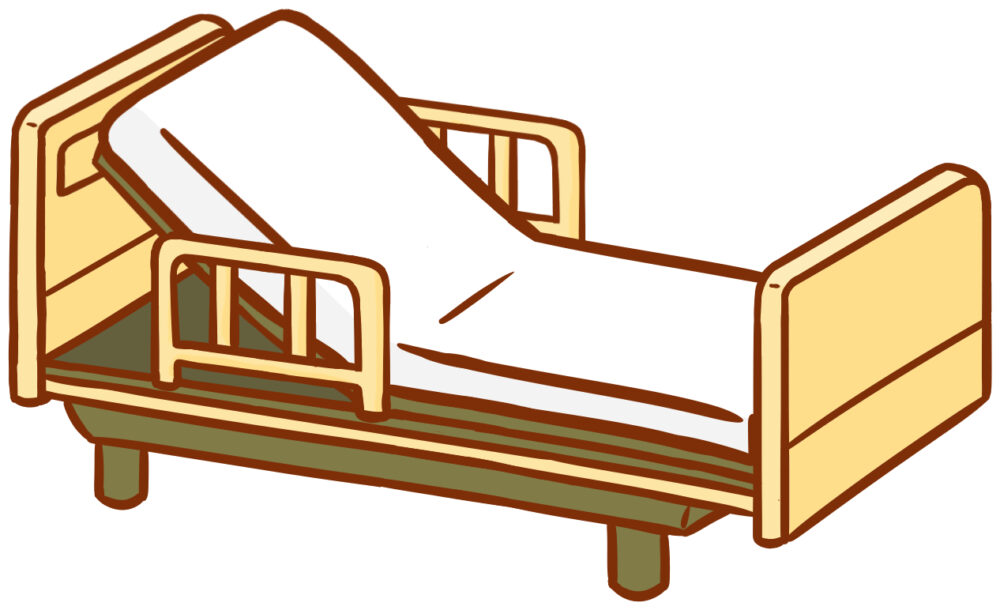
今回から、在宅介護で使う様々な福祉用具について品目ごとにまとめていきます。前回まではご本人さまの状態別に支援ポイントをまとめてきて、その中でも様々な福祉用具の話題が出てきました。状態〜身体機能ごとに同じ福祉用具でも、使われ方や望ましい機能は違ってきます。そのことを福祉用具ごとにまとめていきます。初回は「介護用ベッド」です。
敷布団からベッドへの切り替えのタイミング
お若い頃からベッドを使っていた方はともかく、長年敷布団を使ってきた方がお歳をとってくると、どこかの段階で敷布団からベッドに変えなければならなくなります。タイミングとしては「床から立ち上がるのに苦労するようになってきたら」ということになります。それも床から立ち上がろうとして転んでしまうようになってから、ではなく、少し余裕のあるうちにベッドに慣れてしまう方がよいです。ただし、最初から福祉用具としての介護用ベッドを準備する必要はありません。最初は家具ベッドでも構いませんが、その際に満たすべき条件は次項にまとめます。
家具ベッドから介護用ベッドへの切り替えのタイミング
長年家具ベッドを使っていた方も、身体状態によっては介護用ベッドに変えた方がよいタイミングがくることもあります。家具としてのベッドと介護用ベッドの違いは色々とありますが、家具ベッドから介護用ベッドに切り替える理由としては、「高さ調節ができる」という点と「柵〜手すりをベッドに取り付けられる」という点が大切になります。
家具ベッドは一般的に、例えば椅子の座面よりも少し低めにできています。そして手すりも付けられない訳です。そのような家具ベッドに腰かけた姿勢から立ち上がるのに苦労するようになったら、介護用ベッドに変え時ということになります。もっとも長年使っていた家具ベッドから立ち上がりにくくなったからといって、どうしてもただちに介護用ベッドに変えないといけない、というわけではありません。家具ベッドの脚部分にちょうどよい厚みのしっかりとした木片ブロックを挟み込んで高さを調整し、ちょうどよい位置に福祉用具の「床置き式手すり」を置いてあげてもよいのです。また、介護用ベッドの「高さ調整ができる」「ベッド柵〜手すりが取り付けられる」といった利点とは別に、家具ベッドの方が有利といった点があることも見落としてはいけません。
介護用ベッドよりも家具ベッドの方が有利な点
それは「ベッドの幅」です。介護用ベッドの幅は93cmというものが主流になっています。家具ベッドのシングルサイズは一般的に1mほどありますから、介護用ベッドの方が狭いのですね。差は10cm以内でわずかな差と感じられるかもしれませんが、実際に寝てみると使用感の違いは意外と大きいです。具体的には、幅の広い家具ベッドならば自力で寝返り〜起き上がりできるのに、幅の狭い介護用ベッドではできなくなる、ということが起こります。特にパーキンソン病/症候群といった障害があると、そのような支障状態が生じやすくなります。福祉用具取り扱い店によっては、幅が93cm以上の幅の広い介護用ベッドを扱っているところもあります。
身体機能に問題は少なくても介護用ベッドの方が良いパターン
時に認知症の方で、敷き布団から立ち上がることはできないけれど認知症状のためにベッドから不穏に転落してしまう、という方がいらっしゃいます。そんな方は高さ調整のできる介護用ベッドの中でも、ベッド面が床上まで落ちきる極低床ベッドと呼ばれるものが役に立つことがあります。
つまりベッド上で休んでいる時には敷き布団と同じように床上まで落としきって転落事故を防ぎ、ベッドから離れる時にはベッドを上げて立ち上がりやすいようにしてあげる、という使い方です。上手に使えばご家族さまの、精神的/身体的負担を軽減できます。これも全ての介護ベッドメーカーさんが扱っているわけではありませんが、「認知症者の転落事故防止のために極低床ベッドを」と利用目的と希望を明確に伝えれば、間違いなく準備することができると思います。
介護用ベッドには敷布団は敷き込まない、どうしても敷きたいのなら…
初めて介護用ベッドを使う場合にベッドマットの上にさらに、それまで使っていた敷布団を敷いている様子を拝見することがあります。
なるべくこれまでの「寝心地」を変えたくないとか替えのないベッドマットを汚したくない、といった理由があるのだと思われますが、介護用ベッドに敷布団を敷くと上で説明した通りベッドマットよりも敷布団の方が「幅広」になってしまいます。そうなるとベッドマットの左右端から敷布団がはみ出て、敷布団の左右の端が床に向かって流れ落ちるような形になってしまいます。そこに腰かけようとした時に「お尻が滑り落ちてしまう転落事故」が起きかねません。特に暗い夜間時が危ないですね。
ですから原則として、幅の狭い介護用ベッドにはより幅のある敷布団は敷かないようにしましょう。それでもどうしても介護用ベッドに敷布団を敷きたい場合は、ベッドの左右のうち、起き上がったり立ち上がったり腰かけたりする方の側のベッドマットと敷布団の端をしっかり揃えて床への流れ落ちを無くし、反対側の方で敷布団の余り分を折り上げてしまうなどしてください。
介護用ベッドの「背上げ機能」の使い方~不適切な使い方では事故の可能性も~
家具ベッドと介護用ベッドの違いの一点は、介護用ベッドには「背上げ機能」がある、ということです。(最近は、家具ベッドの中にも背上げ機能のついているものもありますが)もうすでに、自力では立ち上がれない~起き上がりできないといったある程度以上の重症者さまにとっては便利な機能です。しかし、この便利な「ベッド背上げ機能」のために、時には重度な介護事故が起きてしまうこともありますし、突発的な事故にはならなくても本人さまに大変に苦しい思いをさせてしまい拘縮(関節が固まって動かなくなる)や身体変形を悪化させ、むしろ障害の重度化を招いてしまうことも珍しくありません。以下にその原因と予防法をまとめておきます。
「ベッド背上げ姿勢」は基本的に苦しい姿勢、車椅子に座る代わりにはならない
椅子に腰かけた姿勢や重度者用のリクライニング車椅子でも、下腿(膝から先)は垂らし下す姿勢になります。ところがベッドで背中を起こす場合には、下肢全体はベッドの上に乗ったままで、膝を曲げて下腿を垂らし下すことはできません。健常者でも床の上にお尻を下ろして両足を揃えて前に投げ出したままで、手先で足先を触るように体幹前屈すると苦しいですね。膝の裏側のスジが突っ張ります。
ところが介護用ベッドの背上げ機能を使いたい方(=ベッドから車椅子への乗り移りも大変な方)の身体の硬さは、健常者とは比べ物にならないくらいに柔軟性が失われていることがほとんどです。もちろん身体柔軟性は人それぞれであって、つまり背中をどこまで起こしても苦しくならないか?=可能背上げ角度も人それぞれなのですが、それを見極める(評価する)技術が未だほとんど普及していません。
介護用ベッドの背上げは電動であってボタンを押し続ければ本人さまの身体の都合は無視されてどこまでも起こされてしまいます。(75度程度まで背上げされます)無理に背中を上げると膝の裏のスジが引っ張られて、膝がどんどん曲がっていきますし、身体(体幹)が起こしきれずに背中(脊柱)がどんどん押し曲げられていきます。とても苦しいし身体変形が進んでしまうわけですね。どこまで起こして良いか?専門家の検査を受けることができていないのならば、ベッド背上げは「30度まで」にとどめることをお勧めします。30度では「頭」の起き方が少なく「前」よりは「上」を向いてしまう、もう少し頭を起こしたいという時は、枕だけを高くするのではなく肩甲骨の下に畳んだ毛布などを挟み込んで、肩から少し起こすようにします。
30度の背上げでもベッド上で正しい位置で
例え背上げ角度を30度で押さえていても、ベッド上で寝ている位置が不適切だとやはり苦しい姿勢になります。ベッドを背上げする際には「この位置から上方が起き上がっていく」という場所=背上げ軸があります。
ベッド上で極端に足元側に寝ている状態のままベッド背上げすると、背上げ軸が背中の上下真ん中あたりに来てしまいます。つまり背上げボタンを押してベッドを起こしても、身体は「背中の真ん中よりも上」しか持ち上げられないわけです。その位置で60度も75度も背上げされたら、おそらく「脊柱骨の圧迫骨折」を起こしてしまいます
。ベッドで背上げするときには、あらかじめベッド上でなるべく頭側の方に寝ていてもらいます。足元側に下がっていたらあらかじめ頭側に目いっぱいあげておいてあげるべきなんですね。ベッド背上げ軸をなるべく体の足元側になるようにするわけです。そこからベッド背上げすると骨盤も一緒に30度まで起き上がって、脊柱骨が潰れる勢いで背中が丸められ押し曲げられる、ということは避けることができます。
本稿で説明しているのは、「介護用ベッド背上げ機能の使い方の“基本中の基本”」ともいうべきことなのですが、実際には看護介護等の専門職さんの間でも驚くほど知られていません。そんなに難しいことではないので、まずはご家族さまがしっかり理解されて、せっかくの介護用ベッドが本人さまに苦痛を与え、かえって重度化をまねいてしまう、なんて悲しいことが起こらないことを願っています。次回は、ベッド取り付け手すりやエアマットなど、介護用ベッドと合わせて使う福祉用具について説明します。
大渕哲也(理学療法士/介護支援専門員)
1962年新潟県生まれ。
急性期医療機関・慢性期医療機関、特別養護老人ホーム・福祉用具レンタル販売業者等で勤務。
現在は民間介護事業所にて、社内研修・現場アドバイスなどを行なっており、その他民間セミナー業者や各種団体、全国各地の現場からの要請に応じて、研修や現場指導なども行なっている。
Contents
- 第1回 「はじめまして」
- 第2回 「在宅療養介護生活で大切にしたいこと」
- 第3回 「まだ自立レベルでお元気な方」
- 第4回 「歩行に支障が出だしている/認知症初期症状の認められる方」
- 第5回 「歩行に支障が出だしている/認知症初期症状の認められる方 その2」
- 第6回 「実用的には歩けず移動は車椅子だが、自力で立って車椅子へ移る、トイレが自分でできる方」
- 第7回 「介助を受ければ立てる方」
- 第8回 「全介助でも立位は取れない方」
- 第9回 「四肢の変形拘縮があり寝たきりレベルの方」
- 第10回「在宅介護で使う福祉用具①介護用ベッドその1」
- 第11回「在宅介護で使う福祉用具① 介護用ベッドその2」
- 第12回「在宅介護で使う福祉用具②車椅子その1」