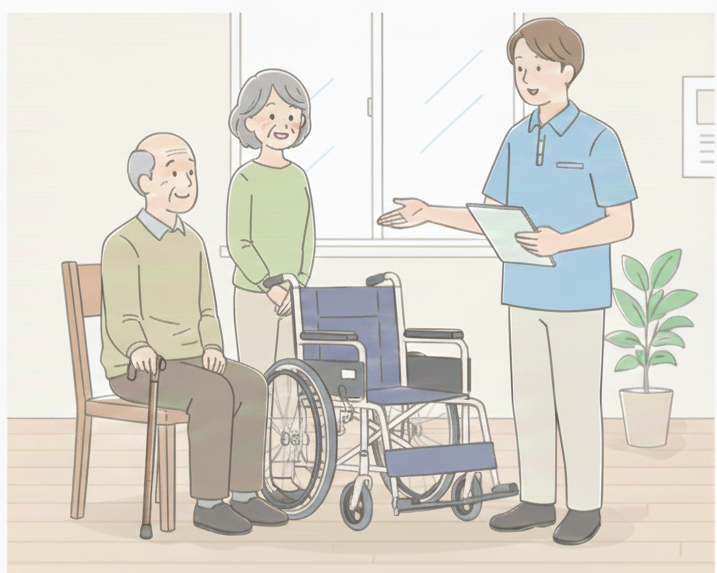第5回「歩行に支障が出だしている/認知症初期症状の認められる方 その2」
公開日:2025/05/19

前回は「歩行に支障が出だしている」「認知症か?単なる物忘れか?はっきりしないけど、明らかに認知機能の変化が認められる」といった方に対する配慮/支援として、
・杖の準備~管理
・痛みと体重の管理
・靴の選択へ歩きやすい靴の選び方
・靴の「中敷き」の大切さ
といった説明をさせてもらいました。今回は「その2」として、住居環境/認知機能への配慮/社会生活の大切さ、について説明いたします。
転倒予防環境整備 ~特に浴室~
歩行に支障をきたしだすといよいよ心配になってくるのが転倒トラブルです。また、それと同時に最初に難しくなってくる生活動作が「入浴」です。浴室での転倒は裸の状態でもあり、怪我もしやすい状況です。ですから歩行に支障をきたしだした方には、安全に、またなるべく長く自宅で入浴できるよう、まずは浴室環境に配慮してあげましょう。
洗身腰かけ
身体を洗うときに習慣的に腰かけて洗う方は多いと思います。ところがこの洗身腰かけですが、実に小さく低い製品もあります。若いころから洗身時に腰かける習慣の方は、浴室がなるべく狭くならないように小さな低い台を使ってきた方がむしろ多いかもしれません。起立歩行の支障状態や立ち座りする際につかまる手すりがあるかどうかなどにもよりますが、安楽に安全に立ち座りできる洗身腰かけを準備してあげましょう。
昔ながらの小さな洗身腰かけは、高さが20cmしかなく座面の広さも狭く仕上げてあります。普通の家具椅子は座面高が42cm程度ですから、半分以下ということになります。福祉用具としての洗身用椅子(バスチェア)もありますがそこまでいかなくとも近年は、市中のホームセンターの浴室用品コーナーで様々なサイズの洗身腰かけが販売されています。高さも30cm、35cm、40cmと選べますが、それら一般向けの腰かけは、やはり座面が狭めに全体として細長く仕上げてあるものが多いようです。
たとえ高めでも狭い座面に立ち座りするのが怖い、ということならば福祉用具のバスチェアも考慮しましょう。福祉用具としてのバスチェアは、高さ調整できる他、背もたれや手すりがついているものも多く、安心して使えます。
浴室内手すり
浴室内に手すりがほしいな、という場面としては、今述べた「洗身腰かけへの立ち座り時」の他に、「浴槽へ出入りする時につかまる手すり」や「浴室?脱衣場の間のドアを開け閉めする時につかまる手すり」があげられます。以下、簡単にこの3種類の手すりについて説明します。
1.洗身台への立ち座り時につかまる手すり
立っている時も座っている時にもつかまることになりますから、「地面に水平に横手すり」よりも「縦手すり」の方が良いと思います。縦手すりの上下は腰かけている時の、また立っている時の、それぞれの胸の高さくらいにあると頼りになります。
また、手すりと壁の距離「隙間」も大切です。足腰が弱ってきている方ほど、立ち座りする時は上半身から頭がお辞儀に動きます。壁から手すりまでの距離「隙間」が狭いとお辞儀ができずに後ろにお尻が落ちていくような動き方になってしまい、危険な動作になってしまいます。立ち座りのための手すりは壁から離して取り付けましょう。壁から30cmくらい離れていれば安心して長く使えるものになります。
2.浴槽へ出入りするための手すり
浴槽の縁の延長上の壁に、手すりが縦に付けてあることがあります。これでも無いよりはずっと安楽になります。同じような機能を持つものとして、福祉用具の「浴槽の縁を挟み締めて取り付けする手すり」があります。これならば工事も不要で準備することができます。
しかし、このような「浴槽の出入りをする時に浴槽縁のところだけに手すり」よりも、本当に頼りになるのは「入っていく浴槽の先」と「浴槽から出ていく洗い場の先」とそれぞれにしっかりつかまるところがあることです。つまり、洗い場から浴槽の中央部あたりまでの壁に、長めに横に手すりがついていると浴槽の出入りが大変に楽に安全になります。高さは浴槽内で立った時にもつかんでいられるよう「洗い場の床で少しお辞儀にかがんでつかめる高さ」くらいがよいでしょう。
3.浴室入り口開け閉めのための手すり
脱衣場と浴室の間のドアには「引き戸」「三枚引き戸」「一枚ドア」「中折れドア」など、様々な種類があります。何にしても開け閉めの時には「立ったままで戸を操作する」ということになります。一般的には横に動かせばよい「引き戸」の方が足腰が弱ってきた方には楽です。
「一枚ドア」が最も大変で、立っている位置から「遠くに向って」開けたり、立っている位置から「身を引きながら」開けたりしないといけません。特に「自分に向って引き開ける」時が危険です。引き戸にしろドアにしろ、「閉まっている戸の取っ手の横の壁」につかんでいられる場所があると楽に安全に出入りできるようになります。短めの縦手すりがあるだけでよいのです。足腰のしっかりした若い方には想像しにくい手すりなのかもしれません。
転倒予防の観点からの寝具
歩行に支障が出だしているレベルですと、寝具として「床に布団かベッドか」迷うところです。長年、敷布団で過ごしてきた方の中には「ベッドでは寝られん!」と切り替えに抵抗を示される方もいますが、当然、床上の布団への立ち座りとベッドへの立ち座りでは、腰かけた姿勢になれる分だけベッドの方がずっと楽です。たとえ日中しっかり覚醒している時には床上に立ち座りできたとしても、夜中に暗い中で半分寝ぼけながらでもトイレに行こうとする時に安全に動けるか?心配です。
転倒予防の観点からも、「心身機能に余裕のあるうちにベッドに慣れてしまう」ことをお勧めします。いよいよ床上の敷布団への立ち座りが大変になり切羽詰まって慣れないベッドに変えるよりは、ですね。その際は何も「介護用ベッド」でなくとも、家具ベッドや何なら若者向けのパイプベッドのようなものでもよいのです。「ベッドに慣れてしまう」それも先々のためにとても大切なことです。
その他の家屋内転倒予防への配慮
玄関まわり
「玄関土間に、靴を脱ぎ履きする時のための腰かけ」「玄関土間と廊下を上がり降りするための手すり」「玄関を出た先の道路までの間の手すり」など、玄関まわりも手すりがほしくなる場所です。
カーペット
家屋内での転倒の原因として意外と多いのが、「カーペット」です。玄関土間からの上り口に置いてある足ふきマットのような小さなカーペットが滑って動いてしまったり、大きなカーペットの端がめくれあがっていたり膨れていたり、といったことが転倒の原因となります。両面テープなどでしっかり止めてあげることをお勧めします。
物忘れや勘違い/認知症初期症状への対応
認知症かな?と思わざるを得ない場面に遭遇したとき、ご家族様はどんなお気持ちになるでしょう?驚き、嘆き、悲しみ、将来への不安、といったお気持ちは多くの家族様が感じることと思います。それも仕方ないことであり当然のことです。ただし、この連載の初回にあえて書かせていただきました、「覚悟を持つこと」「ポジティブな姿勢でいること」が必要です、と。
高齢になった家族に認知症かも?!と思えるサインが感じられた時に、自らの不安や驚きをそのまま言葉に「情けない…お願いだからしっかりして!」とぶつけてしまう事だけは避けていただけたら、と思います。認知症の初期にはご本人様も自身の異変に対する漠然とした自覚や不安感を持つ、と言われています。そのような本人様の気持ちに寄り添い、むしろ絶対に支えて続けていくよ、という態度を伝えてあげてほしいと思います。そして必要ならば早期のうちに、必要な医療受診を進めましょう。
デイサービスの利用も配慮
高齢者でもまだまだお元気な方の場合、個人的な趣味活動や老人クラブへの参加、ご近所の方々との日々の交流など、お歳をとったなりの社会生活を送る事ができます。ところが前回と今回取り上げた「完全な要介護状態ではないけれど完全な自立でもない、心身の衰えが目立ってきている方」の場合、お元気だったころと同じような社会生活を送ることも段々と難しくなっていきます。それとともに家の中に引きこもりがちになっていくと、心身機能の衰えはいっそう激しくなっていきます。そういう残念な状況を避けるためにも、例えば介護保険のデイサービスの利用を考慮しましょう。
要介護度認定調査を受け要支援の判定が得られれば、デイサービスのほか、本稿で取り上げた手すりの取り付けなど住宅改修助成や福祉用具のレンタルや購入などのサービスも受けられるようになります。遠慮なく早めに市役所の介護保険担当課窓口や地域の「地域包括支援センター」に相談してみてください。
大渕哲也(理学療法士/介護支援専門員)
1962年新潟県生まれ。
急性期医療機関・慢性期医療機関、特別養護老人ホーム・福祉用具レンタル販売業者等で勤務。
現在は民間介護事業所にて、社内研修・現場アドバイスなどを行なっており、その他民間セミナー業者や各種団体、全国各地の現場からの要請に応じて、研修や現場指導なども行なっている。
Contents
- 第1回 「はじめまして」
- 第2回 「在宅療養介護生活で大切にしたいこと」
- 第3回 「まだ自立レベルでお元気な方」
- 第4回 「歩行に支障が出だしている/認知症初期症状の認められる方」
- 第5回 「歩行に支障が出だしている/認知症初期症状の認められる方 その2」
- 第6回 「実用的には歩けず移動は車椅子だが、自力で立って車椅子へ移る、トイレが自分でできる方」
- 第7回 「介助を受ければ立てる方」
- 第8回 「全介助でも立位は取れない方」
- 第9回 「四肢の変形拘縮があり寝たきりレベルの方」
- 第10回「在宅介護で使う福祉用具① 介護用ベッドその1」
- 第11回「在宅介護で使う福祉用具① 介護用ベッドその2」
- 第12回「在宅介護で使う福祉用具②車椅子その1」